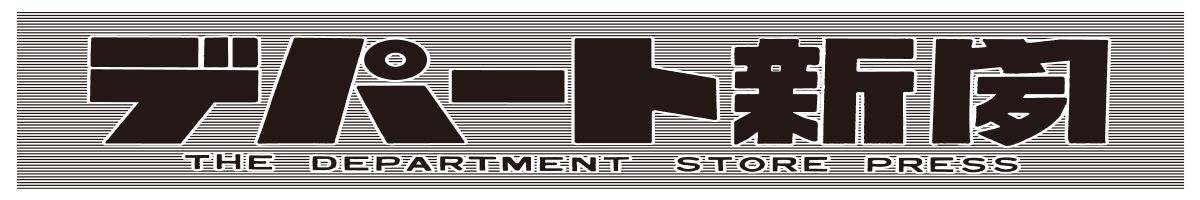デパートのルネッサンスはどこにある? 2022年05月15日号-47(前編)

ユニクロ考(前編)
百貨店のライバルなのかそれとも救世主か
去年10月14日に発表されたファーストリテイリングの2021年8月期(連結決算)は、売上高2兆1329億9200万円(前期比6・2%増)、営業利益2490億1100万円(同66・7%増)当期純利益1698億4700万円(同88・0%増)と増収増益だった。
今や、デパートのキーテナントとしても存在感を増している「ユニクロ」だが、そもそもは郊外型のロードサイドが主戦場だった。食品スーパーやファミレスといった、他のスタンドアローンの店舗との買い回りも重視しているからだ。この戦略は今も変わっていない。どちらにも失礼な言い方になり恐縮だが、ファッションセンターしまむらや西松屋と変わらないポジションであった。
テナント出店のスタートも、イオンに代表される地方= 郊外立地のショッピングセンターの大型核テナントとして、徐々に存在感を増して行ったという印象だ。この辺りは無印良品も同様だ。
それが、もはや押しも押されもしない、国内№1アパレル企業であり、ロードサイドや、ショッピングセンターに止まらず、ついには都心ターミナルの老舗百貨店への出店をはたしている。
好むと好まざるとにかかわらず、百貨店内での存在感は増しており、衰退産業と揶揄されるデパート業界にとっては、もはや無視できない「集客の柱」となっているのも事実だ。姉妹ブランドのGUとともに、引く手あまた、向かう所敵なしの状態だ。
銀座、新宿渋谷池袋、吉祥寺など主要ターミナルでは、ビル一棟を借り上げてユニクロの大型基幹店としている。土地代や賃料は高いが、大型売上が見込めることと、高額な賃料も「宣伝費」だと思えば問題ない。新宿の「ビックロ」の様に、家電量販店との協業という新たな手法にも挑んでいる。
前述の様に無印良品やニトリと同様、都心の大手百貨店へのテナント出店という形態も増えており、駅ビル(ショッピングセンター)との「取り合い、奪い合い」の様相も見て取れる。
ユニクロの生い立ち
創業者の父である柳井等が、山口県宇部市で個人営業の「メンズショップ小郡商事」を創業したのち1963年に法人化、小郡商事株式会社を設立。 1972年に柳井氏の長男である柳井正が入社し、1984年に「ユニーク・クロージング・ウェアハウス」(略称:ユニクロ)を広島県中区に開店した。単なる地方アパレルとして誕生したのだ。
当然その後も紆余曲折のストーリーがあった訳だが、今回の本欄の主旨は「ユニクロ物語」ではないのでこの辺にしておこう。
日本の国民服
さてそのユニクロだが、我々はなぜここまでユニクロに「依存」する様になったのだろう。確かに、若者からお年寄りまで、日本のほぼ全世代がユニクロの「フリース」を着た様は「国民服」とまで呼ばれた時代もあった。この「フリースブーム」は1998年から始まった。当時フリースのアウターはアウトドアブランドで1万円以上が相場だった。それを1900円という衝撃的な価格で売り出したのがユニクロだ。
同年11月に出店した原宿店ではバックヤードから運ばれたフリースが棚に置かれると同時に、客が殺到する光景が見られた。2000―2001年秋冬シーズンには2600万枚を販売し、ヒット商品の枠を超えた社会現象にまでなった。
1 9 9 7 年から2000年にかけて、時代は平成不況に入り、山一證券や北海道拓殖銀行など大手金融機関の破綻が相次いだ。更に消費税率が5%に上がり、景気低迷に拍車をかけ、就職氷河期と言われるほど雇用環境も悪化した。そんなときに頭角を現したユニクロは、その低価格路線でバブル崩壊後のデフレ時代の象徴へと進化して行く。
大震災とコロナ禍
直近10年に限っても、東日本大震災が起こり、人々のファッションに対する価値観も大きく変化した。きらびやかに装うよりも、日々のくらしを充実させることが重要だ、という、悪く言えば「同調圧力」もあったかもしれない。当たり前の毎日を丁寧に暮らすことが本当の幸せだ、として、「ていねいな暮らし」ブームがやってくる。ファッションよりも食や住、ライフスタイルに人々の関心は移っていった。もちろんすべての人が、ではないが。
そうなるとむしろ、おしゃれを頑張りすぎることが「恥ずかしく」なっていく。服はもうユニクロで十分だ。いや、むしろユニクロがおしゃれなのだ、と。過剰にデザインされた服ではなく、シンプルな服を着こなすことがファッションの王道になって行く。もちろん、機能性と着心地のよさが重要であることに変わりはない。「ささやかな、等身大の幸せ」ブームの到来である。
この間に消費マーケットは所有からシェアへと進み、メルカリが生活に浸透した。断捨離やミニマリズムの流行もそれを後押しする形となった。大手アパレルの衰退と併行し、「ブランドに金を払うより、コーディネイトを楽しむ」事がおしゃれな時代になったのだ。
柳井会長兼社長のことば「服はファッション性が全てではない。そんなことに興味がある人はごく一部。服に興味がない人がストレスなく楽しめるのが本当に良い服だ」
価値観の転換
もちろん、日本に限らず、ファッション産業が環境にいちばん負荷をかけているのは間違いない。次から次へと流行を追いかけて、服を「とっかえひっかえ」すること(大量生産、大量消費、そして大量廃棄)ほど、環境破壊に直結することはない。
こうして現在Z世代と呼ばれる若者、彼ら彼女らにとっては、サステナブルファッションが当たり前という時代に突入した。
さらに追い討ちをかけるように世の中はコロナ禍に見舞われた。ステイホームに自粛生活。オンラインでキャンパスデビューした彼らに、「華美」なおしゃれの入り込む余地はなかった。
コロナ禍が「ファッション観」を変えてしまった。Z世代がおしゃれに関心を持つようになってからは、スニーカーにリュックサック、といった名実ともにユニクロのライフウェアが席巻する世の中となったのだ。
テレビのCMを見ても、国民的歌手の桑田佳祐が歌い、国民的女優の綾瀬はるかが微笑んでいる。どこからも文句ひとつ聞こえない、消費の「王道」の完成だ。
SDGsも追い風に
日本という「同調圧力」大国では、目立つことを嫌い、お金を使うことを消費ではなく「浪費」と呼び、悪のレッテルを貼ってしまう。ほんの時々「経済を回すため」という反論も聞こえてくるものの、その声は小さい。
SDGsやサステイナブルが、その小さな声までも黙殺してしまう。そして、一時は若者ファッション市場を席捲した外資のSPAブランドもZARAやH&Mは辛うじて残ったものの、今やGAPは見る影もないし、フォーエバー21も実際には永遠ではなかったワケだ。ユニクロだけが「独り勝ち」といってもけして過言ではない。
※ここでは無印良品はやや守備範囲が異なるので言及しない。しまむらもSPAではなく仕入れ販売の商売なので同様だ。
※SPAとは( 用語解説)
製造から販売まで垂直で統合させた業種。SPAは消費者ニーズに迅速に対応できることから、無駄なく効率的な販売業態だと言われている。SPA 「s p e c i a l t y s t o r e retailer of private label apparel」の略語。製造小売業と訳される。
アパレル製造小売業で世界ランキング上位の「ZARA(ザラ)」を擁するインディテックスや「H&M」のヘネス・アンド・マウリッツ、「UNIQLO(ユニクロ)」や「G U( ジーユー)」で知られるファーストリテイリングもSPA企業。
そもそもSPAは、アメリカの衣料品小売大手ギャップ(GAP)から生まれた造語であり、1987年の株主総会配布資料の中で、創業者のドナルド・フィッシャー会長が自社の業態を、SPAと述べたことによる。
元々SPAは、独自のブランドを販売する衣料品専門店という意味だったが、1990年代以降概念が広がり、現在では素材調達から、商品の企画や生産、販売までのすべての工程を一貫して行う企業をSPAと呼んでいる。
話をユニクロに戻そうユニクロの製造工場のある中国ウイグル自治区での人権問題や、ウクライナ侵攻に伴う在ロシア店舗の閉店の遅れ等で、揶揄されることはあっても、大きなマイナスイメージは被っていない。
ハイブランドとの協業
以下、有名ブランドとの最近のコラボレーションを列挙する。ジルサンダー2009年から約2年に渡り、ジル氏はコラボライン「+ J」のデザイナーとなった。このコラボラインは世界的にヒットし、ユニクロの世界的評価を一気に高める事となった。マメクロゴウチ「Uniqlo and Mame Kurogouchi 下着と洋服の境界線を越える、新しいインナーウェアコレクション。2022年4月29日より販売開始。マルニ「UNIQLO and MARNI シンプルな中にMARNIらしい大胆で遊び心溢れるカオスな世界観が融合したコレクション。2022年5月20日より販売開始。
もはや下着1枚、靴下1足さえ持っていない、という人は稀であろう。かく言う筆者も、もちろん例外ではない。フリースも、ウルトラライトダウンも、アンダーウェアも季節によってヒートテックとエアリズムを使い分けている。当然靴下も。気を付けないと上から下まで「オールユニクロ」スタイルという有様も何度かある。よく考えると「ちょっと恥ずかしい」が、なにしろ日本の国民服なのだから大丈夫だ。
百貨店のテナント化
例えば大手百貨店は、都心ターミナル駅前の一等地に店舗を構えていても、売上の低下→百貨店平場の縮小→テナント不足が深刻化し、昨今は集客核となるメガストアの積極導入を検討する。
どうせ出店してもらうなら「ブランド力」が強く、更に単店で客を動員できる大型店の方が、百貨店本体への波及効果が期待できる、という計算となった。そして、本来は自店ファッションとの競合から誘致をためらっていた、大型アパレル「ユニクロ」の出店となったのだ。
東急ハンズや無印良品、ニトリ等も同様の理由で次々と百貨店に出店した。百貨店に出店することにより、ユニクロはロードサイドの量販店イメージを払拭し、長引く日本のデフレ下も相まって、そこそこのブランドとして、顧客に再認知されるという、好循環もあった。百貨店とのWIN―WINの関係が構築された訳だ。
ここまで、「ユニクロ」をNO.1アパレルブランドなどと、褒めそやしてきたが、盤石に見える時こそ、危機が迫っているというのが世の常だ。首都圏の主要ターミナルを制覇し、都心の大手デパートに核テナントとして出店すれば、国内アパレルとしては双六の「上がり」であろう。
勝ち組からの失速
ただ、NHKの大河ドラマではないが「驕る平家は久しからず」である。盛者必衰は、小売業界においても定説であり、ダイエー、そごう・西武、レナウン、ワールド、オンワード等々、枚挙にいとまがない。ユニクロがそうならないとは誰にも言えないのだ。
「無双」状態のユニクロの「死角」を探るべく、運営会社であるファーストリテイリングが公表する国内ユニクロ事業の既存店売上高推移を見てみよう。
ユニクロは8月期決算であるため、今期は2021年9月から始まっているが、21年12月までの推移は決して好調といえるものではなかった。9月が前年同月比19・1%減、10月が同4・8%減、11月が同4・6%減、12月は「感謝祭」があったにもかかわらず、同11・1%減と落ち込んだ。
もちろん売上が2兆円もあれば十分だし、負け組として論じること自体、ナンセンスなのだろう。ましてや足元では、新型コロナウイルスの感染拡大という要因が大きい。
だが、それだけでは説明できない要因もある。

デパート新聞編集長
以下次号 後編へ続く
連載 デパートのルネッサンスはどこにある?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年02月01 日号-第131回 「食べる本屋さん」の「ニジコミ」企画とは?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月15 日号-第130回 池袋西武の初売りに行ってきた。脱デパートは非デパートなのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月01 日号-第129回 ジャパニーズホラー再考
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月15 日号-第128回 新宿伊勢丹に学ぶ
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月01 日号-第127回「モノ消費からコト消費」のその先は
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月15 日号-第126回 お化け屋敷はデパートの救世主なのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月01 日号-第125回 デパートを巡る様々なニュース 後追い記事の後を追う
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月15 日号-第124回 百貨店の閉店で街は寂れたのか?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月01 日号-第123回 池袋西武の現在位置 ―代表と店長と―
- ヨドバシカメラの素質と資質