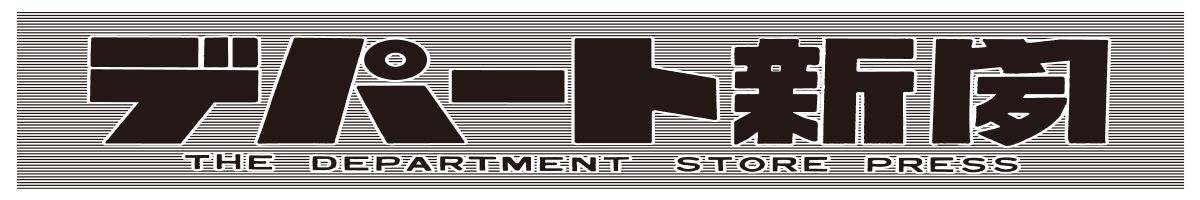デパートのルネッサンスはどこにある? 2024年03 月15日号-88

新所沢パルコの閉店から考える
百貨店の閉店が相次ぐのはナゼ?今後百貨店はどうなる?
本題に入る前に、本コラムが追い続けている池袋西武の動きを確認しておきたい。
先ずは半年ほど遡(さかのぼ)って、2023年10月27日の東洋経済オンラインの記事を見てみよう。
”池袋西武で進む「トンデモ改装」仰天の中身” というセンセーショナルなタイトルの記事だ。覚えている方も多いと思う。
百貨店そごう・西武の西武池袋本店で「百貨店の常識とかけ離れた、とんでもない改装」が実施されようとしていることがわかった。
セブン&アイ・ホールディングスは(2023年)9月1日、そごう・西武を米投資ファンドのフォートレス・インベストメント・グループに売却した。その後、フォートレス日本法人幹部がそごう・西武の代表取締役に就任し、(中略) そごう・西武はフォートレス主導で再建を進めている。
旗艦の西武池袋本店は、関東地区の百貨店として伊勢丹新宿店に次ぐ第2位の売上高を誇る。フォートレスと連携するヨドバシホールディングスが西武池袋本店の土地と建物を取得し、家電量販店の「ヨドバシカメラ」を出店する計画が固まっており、百貨店としての売り場面積は現在の半分程度となるため、店舗の改装や運営について計画の策定を進めている最中だ。
池袋西武で進む「トンデモ改装」仰天の中身
アパレル売場の大幅縮小を指示
新経営陣(フォートレス) は「百貨店や小売業の常識とかけ離れた指示を出し、とんでもない改装を進めようとしている」とし、売上げが芳しくないアパレル領域に手を突っ込み、売り場の大幅縮小を指示。アパレルといえば百貨店最大の柱ともいうべき存在だが、容赦なく切り捨てる考えだ。
その上で、高級ブランドや食料品については、出店しているテナントを売上高や利益貢献度の大きい順に並べ、高級ブランドについては上位10社程度、食料品については上位20社程度に絞ることが俎上に載せられているという。
これに対し、そごう・西武関係者は「百貨店のビジネスモデルを無視した、あまりに機械的な商品政策だ。これではフォートレスが買収時に掲げた「"百貨店の再成長”は達成できない」と憤(いきどお)り、記事では最後に、他の都心百貨店の幹部の言として「池袋西武はもう終わる」とまで断じている。
売場面積4割減
この件に関し、2月の末に池袋西武に取材したところ、池袋西武のパルコ寄り(本館北側)のテナントとの契約は2024年の7月か8月までとなっており、全体の西武百貨店の売場面積は従来の6割(40%減)となる、としている。正に激減するのだ。
但し、デパ地下(食品)、化粧品、ラグジュアリーブランドの面積は現状レベルを維持し、売上は8割(20%減)、利益はスタッフの異動などにより100%維持で計画している、とのことだ。
※もちろん売上や利益の数字については机上の空論だが。
既にB2F南側の食品スーパー「ザ・ガーデン」は1月31日に閉店しており、この区画に現状のデリカ(総菜)ゾーンなどを移動させる、という。
上記の大改装により子供服はほぼ無くなり、レディス、メンズや雑貨の面積も大きく減少する。尚、本紙2月1日号の本コラム冒頭でルイ・ヴィトンの去就(西武外への移設の可能性)について「まだ決まっていない」と述べたが、正式に池袋西武に「居残り」が決定した様だ。
いろいろな力が働いてのことだろうが、筆者の予測は「まんまと」外れた。お詫びして訂正する。
新宿伊勢丹
因みにルイ・ヴィトンは、3月20日に新宿伊勢丹メンズ館の2Fに出店する。
現在改装中のメンズ館2Fには「ルイ・ヴィトン」のほか「ディオール」「セリーヌ」「バレンシアガ」「メゾン マルジェラ」「バーバリー」「コム デギャルソン」がオープンする。
現状ルイ・ヴィトンは明治通りを挟んで伊勢丹本館の真向かいに位置しており、渋谷のミヤシタパーク同様、新宿でもメンズアイテムを独立させ、インバウンドや富裕層対応を強化する様だ。
地図を見れば明らかだが、池袋西武のルイ・ヴィトンは東京の拠点の中で「最北」となる。
埼玉顧客のゲート( 入り口) として、既存店である池袋西武にあれば、その役割は充分果たせる、という判断であろうか。さて、ここから本題だ。
「Dayday」
タイトルにある新所沢パルコ閉店の顛末(てんまつ) を、日本テレビの情報バラエティ番組「DayDay」が3月7日放送の「ナゼ?ナゼ?」のコーナーで特集した。
余談だが、当初は閉店翌日の3月1日に放送予定だったが、急遽、大谷翔平の結婚報道が飛び込み、一週間延期となった。
デパート新聞にも取材の依頼が入り、筆者もほんの少しだけ出演した。本コラムのテーマとリンクする題材なので、番組の内容を抜粋し再録させてもらう。
全国で百貨店の閉店が相次ぐのはナゼ?
埼玉県所沢市の新所沢パルコが40年の歴史の幕をおろした。いま日本全国で百貨店が閉店に追い込まれている。日本百貨店協会によると1999年は311店舗だったが2023年180店舗とおよそ4割減ったという。しかし売上を拡大している百貨店もある。業績アップの店舗のヒミツは?
※お断りするまでもないが、厳密にはパルコは百貨店(デパート)ではないが、都心、地方を問わず、様々な「商業施設」が閉店しているのは事実だ。そして本紙デパート新聞では何度も取り上げている題材だ。
そもそも本コラム「デパートのルネッサンスはどこにある?」の第一回は、4年前の2020年4月15日号「山形の百貨店『大沼』が自己破産を申請」と題し、大沼デパートの破綻と閉店を特集したのがスタートだった。
40年の歴史に幕「最後の日」に密着
新所沢パルコの閉店について、館内の店員は「コロナで変わった」などと思い出を語る。館内には客の寄せ書きが飾られている。地元の人に愛されながら41年の幕を下ろす。午後8時、地元の人が集まり最後を見守った。
閉店の理由についてデパート新聞の担当者は「建物の老朽化」という。
今年島根県松江市の一畑百貨店も、地元の人に愛されながら閉店した。理由は近くに郊外型ショッピングモールができたことや、ネット通販の利用が増えて客が減ったためだ。
地方は過疎化に直面しているため、客も働き手もいなくなり商売がなりたたない。結果、島根の百貨店はゼロとなった。他にも山形県や徳島県も百貨店はゼロとなっている。今年7月には岐阜県もゼロとなる見込みだ。
都心でも、街の再開発により、渋谷の東急百貨店も閉店した。去年1月には髙島屋立川店が閉店し専門店となった。
そんな中、ある取り組みで業績をのばす百貨店もある。東京駅隣接する大丸東京店だ。
業績UPの店舗も
大丸東京店は惣菜や土産(みやげ)など種類が豊富だということで、客が集まる。1階を食品フロアにしたことで旅行客を取り込んでいるのだ。さらにイベントを開催し若い世代のリピーターを増やしている。コロナ前と比較し10%業績アップした。 さらに山梨県の百貨店「岡島」は老朽化した建物での営業をやめ、去年商業ビルの1階フロアに移転した。移転で売場面積は4分の1となり無駄な経費が減ったという。
さらに新しくなったことで若い客も増えた。売場面積は減ったが平日の平均買い物客数はおよそ3500人と変わらず、利益が増えているという。
百貨店にどのくらい行っている?アンケート
視聴者に「百貨店を利用する頻度は」と質問したところ
「毎週行っている」12%
「毎月行っている」22%
「ほとんど行かない」66%
で「ほとんど行かない」が圧倒的多数だった。
※混ぜっ返す訳ではないが、12%と22%で合計34%は「百貨店に行っている」と回答しているのだ。
これは決して低い数字ではないと思う。少なくとも「行かない人が」圧倒的、というのは言葉の綾(あや)だとしても、伝え方が極端だ。
この辺りのテレビの表現の仕方には、ちょっと首を傾げたくなる。番組批判ではないが。
常識を覆すスゴイ百貨店が続々
日本全国の百貨店を制覇したという放送作家・デパート愛好家の寺坂さんの話
百貨店の魅力を聞くと寺坂さんは「外観は普通のビルだけど、中に入ると街になっている。宝箱や玉手箱のようなものですかね」と答えた。
「閉店が相次ぐ理由」について寺坂さんは「お子さん連れでいらっしゃる方が減った。昔は『迷子のお知らせ』がすごくよく流れていたけど、最近はあまり聞こえない。ベビーカーで来る方も少なく、郊外の大きなショッピングモールに行き、映画も見て買い物もして、ゲームセンターもあるし・・・と何でも揃うので、そちらに行かれているんじゃないですか」と話した。
今後百貨店はどうなる?工夫で起死回生も
とにかく人を集める。これまでデパートは買い物をする場所だったが、最近のデパートは人が集まるように工夫している。とし、4つの好事例を紹介した。
1.松坂屋静岡店
7階が水族館になっている。ユニークな取り組みであり、平日は満足度で入館料を決めるというシステムになっている。
2.松山三越 ( 愛媛県松山市)
道後温泉の老舗が運営するホテルが中に入っている。各部屋にフィンランド式のロウリュサウナを完備している。
3.東武宇都宮百貨店栃木市役所店
1階が東武百貨店で2~5階が市役所。もともと百貨店だったビルが閉店し、居抜きで市役所が入り、1階だけ百貨店が残った。
4.藤崎(宮城県仙台市)
ここでは百貨店同士のコラボ企画をしており、藤崎の中に埼玉の丸広百貨店、長野の井上百貨店、広島の福屋がイベントで入店し、それぞれのデパートのイチオシ商品が仙台の藤崎に出品するという珍しいパターンだ。
「デパートの人はその街のことを知り尽くしているので、マニアックな商品が並ぶ」などと話した。
※ここまで寺坂氏の解説。
視聴者は
「百貨店の思い出」について聞いたところ、「百貨店に勤務していますが、お客様の数は年々減少しているようです。夫と出会った場所なので大切な場所です」
「小さい頃にお子様ランチを初めて食べたのが今でも覚えてます!なんでもある魔法の場所が百貨店っていうイメージですね」などの声があった。
最後にMCの武田キャスターの「思い出の詰まった百貨店、残ってほしい」という親身な言葉が印象的だった。
※DayDayは以上だ。
閑話休題
本コラム2021年3月15日号の記事から「結論めいた事」を再掲載する。
新陳代謝と淘汰
街の賑わいの一翼を担っていた商業施設が、マンションやホテルに取って代わられる、という事案は多く、全国の地方百貨店跡でも、同様の案件が散見される。
尚、このテーマは、2020年4月に掲載した、山形の大沼デパートの破綻を皮切りに、本紙は何度も取り上げている。
都心、地方、郊外を問わず、不振に陥った百貨店、商業施設は撤退を余儀なくされる。それは小売を生業とし、顧客を相手に商売をする者の宿命である。
●地方百貨店の閉店理由
- 過疎化の進行による客数の減少
- オーバーストアによる競合負け
- ビルの陳腐化、老朽化
以上の理由はある意味仕方がないという側面もある。
人間の身体と同じく、商売でも新陳代謝は必要だからだ。そして、人類の進化同様、熾烈な生存競争の果てに、淘汰されてしまうリスクは、常につきまとう。以上だ。
マスコミ批判ではなく
日テレのDayDayのインタビューで、筆者はこの閉店理由について、三つすべて述べたのだが「老朽化」だけが切り取られてしまった。
いや、これは単純なマスコミ批判ではない。テレビ局は視聴者に興味のない「理由」にまで言及する余裕はないのだ。
同様に、地方百貨店を存続させるには、営利だけでなく、公益という理念とのバランスが不可欠である旨を説明したが、もちろん割愛されてしまった。
因みに地方百貨店の閉店について「地方は過疎化に直面しているため、客も働き手もいなくなり商売がなりたたない」という話はカットされずに放送されていた。念のため申し添えて置く。
最後に、
番組内で密着取材を受けていた、新所沢パルコ営業担当者に「お疲れ様でした」という慰労の言葉を送り、筆を置きたい。
おおらかなキャラクターで、お客様やテナント店長の心情に寄り添っているのが、見て取れた。パルコでもデパートでも、お客様は館の閉店に際し「ノスタルジー」に浸り、自身の「思い出」を想起する。
お客様インタビューを聞いていると、引退するスポーツ選手への愛着の様な感覚がある。ピークを過ぎた選手(や商業施設)への悲哀を共有できるのだろう。
人も施設も「去り際」が大事だという事を実感した。

デパート新聞編集長
連載 デパートのルネッサンスはどこにある?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月15 日号-第130回 池袋西武の初売りに行ってきた。脱デパートは非デパートなのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月01 日号-第129回 ジャパニーズホラー再考
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月15 日号-第128回 新宿伊勢丹に学ぶ
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月01 日号-第127回「モノ消費からコト消費」のその先は
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月15 日号-第126回 お化け屋敷はデパートの救世主なのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月01 日号-第125回 デパートを巡る様々なニュース 後追い記事の後を追う
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月15 日号-第124回 百貨店の閉店で街は寂れたのか?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月01 日号-第123回 池袋西武の現在位置 ―代表と店長と―
- ヨドバシカメラの素質と資質
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年9月15 日号-第122 回 インバウンドバブルの終焉?