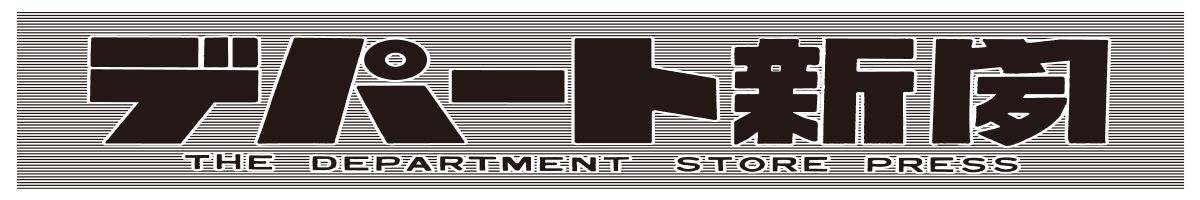デパートのルネッサンスはどこにある? 2022年11月01日号-56

Contents
富裕層シフトの必然
本コラムで何度も取り上げている都心百貨店の「富裕層シフト」について、改めて検証したい。
本コラム2021年11月15日号と12月1日号で都心老舗百貨店の「富裕層シフト」について記した。元々、外商に強く、上顧客を抱えていた三越伊勢丹、髙島屋、大丸松坂屋などの大手百貨店は、所得が上がらず(当然増税により、実質可処分所得が目減りし)疲弊する中間層ではなく、富裕層に注力する様になった。
加えて、この2年半は、コロナ禍が、その色合いを更に鮮明にした、と言う事だろう。
ラグジュアリーブランドのファッション、宝飾、時計から現代アートに至る、様々なアイテムが「裕福な顧客」向けにカスタマイズされていった。都心の百貨店は外商部隊の強化だけでなく、ネット販売やサブスク、といった新たな販売手法を駆使し、ニューリッチ層に向けた品揃えを強化しているのだ。
ここで少し時代を遡る。
平等意識
30年前にはまだ「一億総中流」というコトバが残っていた、と記憶している。日本人の大多数が、大金持ちではないが、決して貧乏でもなかった時代だ。
歴史的に見て、当時日本の社会が本当に「公平、公正」であったかどうかは定かではない。もちろん男女雇用機会均等法は成立していたが・・・
だがしかし、労働者は、少なくとも今よりは「平等」の意識は強く持っていたのではないかと思う。「一生懸命働けば、クルマも買えるし、結婚して、ローンを組めば、マイホームも夢ではない」という昭和ドリームが、平成に入ってもギリギリ残っていたのではないか。
そしてここが重要なのだが、所得は右肩上がりに増え、従って彼ら彼女らの購買意欲は至極旺盛であったのだ。
もう一つ重要なのは、日本の人口がまだ増えていたことだ。
※因みに日本の人口のピークは2008年の1憶2808万人だ。
もちろん、田舎から都心への人口流入により、地方の過疎化は進行し続けていたが、都市部の人口は増えていたのだ。
我が世の春
そして当然、小売の王様である百貨店は「我が世の春」を謳歌した。
※前号の新宿小田急の記事を売り返って見よう。世界一の乗降客数を誇る新宿駅直結の立地を生かし、百貨店全盛の1991年度には売上高1784億円を記録した。
今から31年前の事だ。デパートにとっての「古き良き時代」はマス( ほとんどすべての消費者)が顧客であった。当然百貨店はマスマーケティングにより、誰もが「ちょっと背伸びをすれば」買物を楽しめる「場」を提供していた。そしてそれは日本中のどの都市でもそうであり、そこには目立った地方格差は存在しないか、少なくとも存在しない様に見えた。
格差意識社会
実際には、当然所得格差は存在していたが、「格差意識」は希薄であり、今の様に誰もが「格差社会」を意識してはいなかったのだ。逆に、現代は「格差意識社会」と呼ぶのが相応しいのかもしれない。当然、裕福ではない側が、格差を「意識させられる」社会だ。それは、30年前は「中流」と呼ばれた、ごく普通の中間層が、今や「裕福になることを期待出来ない社会」に変貌したのだ。30年前のこの時代は日本中の百貨店が文字通り「みんなのデパート」であった。売る方も買う方も、ともにある意味「幸せな時代」だったのだ。いかんいかん、また「昔は良かった」症候群が始まった。歳は取りたくないものだ。
※本紙デパート新聞社社主が上梓した「みんなのデパート」については、10月1日号で詳しく解説している。是非、参照願いたい。
中間層の縮小
最近、にわかに議論の的となっているのは「日本の平均賃金が約30年間変わらない」ことだ。
それにより他の先進国と比べて、相対的に貧しい国になった。そしてコロナ禍を機に、所得格差が一段と広がった。昨今の急激な「円安」がこれに拍車をかけているのは、言うまでもない。30 年間、今の今まで選挙の争点にならなかった事が不思議に感じる。何だか「騙された」様な感じだ。少子化問題も同じだが・・・
もちろん、アベノミクスの是非を論じても、今更感が漂うだけだ。
一般論で恐縮だが、個人消費にかかわる小売業は、国の経済政策の影響を強く受ける。中でも長い歴史を持つ百貨店は「時代を映す鏡」だから、余計にそうなのだろう。
高度経済成長を経て、一億総中流と呼ばれた時代に絶頂を迎えた百貨店は、バブル崩壊後のデフレ、そしてコロナ禍を経て、今まさに「富裕層シフト」を鮮明にしている。という話は本コラムで3回に1回は言及しているので、購読者諸氏は耳タコであろうが、ご容赦ねがいたい。
マスマーケティング - 終わりの始まり
三越伊勢丹ホールディングスの細谷社長は、就任当初から、事業戦略の目玉として外商の強化を打ち出している。彼は「マスから個へ」と表現する。曰く「百貨店はずっとマス狙いだった。広く網をかけるのが常識だった。今後は個のお客さまに照準を合わせる。個々のお客さまとの付き合いを深める商売に変わる」と。
従来、百貨店は駅前の一等地に巨大な店舗を構えて、とにかく幅広く集客することが常識だった。大勢の人を集めて店舗内を回遊させれば、売場にお金が落ちるからだ。
だが、中間層の百貨店離れが進んだことで(この表現は語弊がある。顧客は「離れざるを得なかった」のだ、主に経済的な理由によって)不特定多数のマス=大衆、に網を広げるビジネスモデルは限界を迎えた。ロイヤリティの高い顧客=富裕層と密接につながることが、百貨店の高収益に直結するからだ。
ニューリッチ
今後、大手百貨店各社は、ニューリッチと呼ばれる30〜50代の新しい富裕層に向けて、デジタルなどを駆使した新しい外商ビジネスを築こうと、知恵を絞っている。百貨店のネットワークと総合力を用いて、衣食住から、遊び、学び、果ては資産形成や終活に至るまで、ワンストップでさまざまなコンテンツを提供する目論見だ。現時点で、この分野は百貨店の独壇場と言って良い。
岸田内閣が掲げる「資産所得倍増」は、中間層の所得の上昇を訴えている。それが実現できるかは未知数であるし、もちろん、到底数年で成し得る課題ではない。
生き残りをかけた百貨店は、まず富裕層市場にターゲットを絞り、そこに経営資源を集中しているのだ。
「富裕層」争奪戦
百貨店による富裕層の争奪戦が激しさを増している。中間層の百貨店離れに歯止めがかからず、インバウンドの回復に、やっと明るい兆しが見えて来た中、安定した収益を稼ぐ外商ビジネスの重要性は相対的に高まるばかりだ。
※デパートにとっては幸いと言うか(皮肉な事に)急速に進む円安により、訪日外国人の富裕率が相対的に高まっている。
外商は日本の百貨店独自のユニークなビジネスモデルで、富裕層の分厚い顧客基盤は、他の小売業やECプラットフォームがうらやむ存在だ。その財産を今の時代に合わせて進化させることが、百貨店の生き残りのカギ になるといって良いだろう。
以下、具体例を2つ挙げよう。
三越日本橋本店
同店で8月17日に始まった「三越ワールドウォッチフェア」はロレックス、ブレゲ、ウブロ、パテックフィリップ、ヴァシュロン・コンスタンタンなど、数百万円から数千万円の希少なモデルが勢ぞろいし、全国から時計ファンが押し寄せる人気催事だ。
昨年の開催では前年比1.5倍の12 億円を売り上げ、過去最高を記録した。
担当バイヤーに聞くと、今回も過去最高額を大きく更新した、とのこと。「すでに外商のお客さまの事前商談で1億円を超える時計の注文をいただいている。1〜7月の時計売場の売上も、前年同月比1・5倍で推移しており、お客様の購入意欲をひしひしと感じる」という。
三越伊勢丹ホールディングスは、今年4月には、個人と法人、店舗などで分かれていた外商組織を統合し、富裕層133万世帯にターゲットを絞っている。
顧客から吸い上げた声を共有し、属人的な商売からの脱却を目指す、という。外商スタッフだけでなく、専門知識を持ったバイヤーも外商チームに組み込み、顧客の満足度を高める狙いだ。
JR名古屋タカシマヤ
2〜4階のラグジュアリーゾーンに、新規5ブランドを導入、8ブランドをリニューアル。更に7階にも同ゾーンを拡大。
更に11月には「エルメス」の売場を拡大刷新するほか、ジュエリーの「グラフ」など3ブランドの売場を2023年春以降、順次リニューアルする。
新ブランドとしては、先行オープンの形で2月に「マノロブラニク」が4階に、4月に「モンクレール」が2階に登場。ラグジュアリーブランド数は各階合計で34となる。
さらに、7階紳士売場にラグジュアリーゾーンを新設するほか、2023年春以降も、新ブランド導入を継続する。
こうして、ラグジュアリーゾーンの総売場面積はリニューアル前の1.5倍以上に拡大する。
JR名古屋タカシマヤは、JR名古屋駅と直結したJRセントラルタワーズの核店舗として2000年に開店。運営はJR東海と髙島屋の合弁会社JR東海髙島屋で、地下2階から地上13階と51階に売場を構え、売場面積約1700坪を誇る、名駅エリア最大の百貨店だ。
名古屋駅直結という地の利もあり、2000年度の年間売上約600億円を2021年度に約1400億円まで伸長。ラグジュアリーゾーンに限れば、2021年度の売上が2000年度の6倍以上。次の時代の消費を担うミレニアム及びZ世代といったニューリッチ層からの支持に期待を寄せる。

デパート新聞編集長
連載 デパートのルネッサンスはどこにある?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月15 日号-第130回 池袋西武の初売りに行ってきた。脱デパートは非デパートなのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月01 日号-第129回 ジャパニーズホラー再考
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月15 日号-第128回 新宿伊勢丹に学ぶ
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月01 日号-第127回「モノ消費からコト消費」のその先は
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月15 日号-第126回 お化け屋敷はデパートの救世主なのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月01 日号-第125回 デパートを巡る様々なニュース 後追い記事の後を追う
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月15 日号-第124回 百貨店の閉店で街は寂れたのか?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月01 日号-第123回 池袋西武の現在位置 ―代表と店長と―
- ヨドバシカメラの素質と資質
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年9月15 日号-第122 回 インバウンドバブルの終焉?