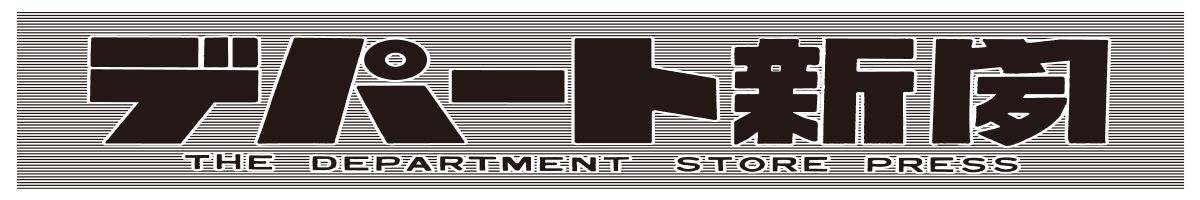デパートのルネッサンスはどこにある? 2021年11月01日号-35

コロナ禍の1年を振り返り、これからのデパートを考える
真のルネッサンスには「変革」が不可欠
日本におけるコロナ禍は、10月の声を聞き、急激に収束している。
この1年半の間、日本の経済と国民の生活を翻弄し続けて来たコロナが、である。我々が常にその数字を( ほぼ毎日)気にし続けていた「新規感染者数」というコロナ感染のバロメーターが、急に下ったのだ。
ニュースでは、ほぼ1年ぶりの水準、と言っている。一般市民にとっては、予想できないレベルであり、「いわゆる専門家」達も、誰もちゃんとした説明が出来ないらしい。
もちろん、ワクチン接種率が一定水準を超えたから、という模範解答はあるものの、あれだけ政府も地方自治体も、加えて報道機関も連呼していた「人流」は抑えられたのか?みな半信半疑なのだ。
今になって、本来ウイルス感染には季節性があって、1年前の年末年始同様に、今度は第6波が到来する、と警告する「識者」もいる。それが理由なのか、それとも「疑り深い」国民性なのか、「コロナは一旦収束したから、先ずは良かった」という意見はあまり聞こえて来ない。半信半疑どころか1億総「疑心暗鬼」状態だ。持前の同調圧力と横並び発想に支えられて、「恐る恐る」以前の日常を思い返し始めている最中だ。日本全体が、心のリハビリ状態なのかもしれない。
2020年10月
去年の今頃も「世間のムード」は似た様な感じだった。
本紙2020年10月1日号の本欄記事を抜粋した。
皆が警戒の指標としている、東京都の新規感染者数はここ連日は195人と、微妙に200人を下回ったものの「第2波は8月中旬には既にピークアウト」と報じられてから1ヶ月以上の間、一進一退の状況が続いている。誰も、胸を張って「アフターコロナ」だと主張できる状況には至っていない。尚、全国の累計感染者数は、8万人を超えた。死者数は1500人超だ。
因みに1年後の2021年10月23日の累計感染者数は、170万人を超え、死者数は18000人だ。
きわめて大雑把な計算で申し訳ないが、この1年で感染者数は20倍、死者数は10倍となったのだ。2021年の8月をピークとした、いわゆる第5波がいかに大きかったか判る。最近のニュースでは一切聞かなくなった「デルタ株」の影響なのか?答えは判らないが。続けよう。
一方で、野球観戦や映画館への入場規制緩和や、来月からのGoToキャンペーンへの東京参加、入出国制限の緩和などが次々と発表されている。我々は否応なく、ニューノーマルという、以前とは異なる「日常」に戻ることを示唆されている様だ。前号でも言及したが、年が明けて、ワクチンを打ち、何とかオリンピックを開けば、その時はもう少し国民の間にも「乗り切った感」が醸成されるのかもしれない。(2020年10月1 日号)
今、自分の書いた記事を読み返すと、中々の楽観論者だったな、と恥ずかしいし腹立たしい。
コロナはこのまま収束する、と考えている人間の論調だ。「収束してほしい」という願望をそのまま述べているだけだが「楽観バイアス」というのはこういうことを言うのだな、とため息がでる。
もちろん、だから第6波への「警戒」は必要だが、リバウンドを恐れて、自粛生活を継続しよう、というのは多分間違っていると思う。我々がこの1年で学んだのは、アフターコロナの世界は訪れず、ウィズコロナの時代が到来したことを受け入れるしか、選択肢はない、ということだ。仕事をし、買物をし、旅行やエンタメも楽しめば良い。色々気を付けながら。
人類はいままで様々なパンデミックとも、そうして折り合いをつけて来たのだから。
さて、我らが百貨店業界の苦境は、本紙前々号( 2021年10月1日号)でもお伝えした。繰り返しになるが、デパートの苦境の「原因」はコロナではない。コロナ禍以前から「衰退」は始まっていたのだから。インバウンド需要という名のドーピングにより都心百貨店は「持ち直した」かに見えたが、その間も地方百貨店の閉店ラッシュは静かに進行し続けていた。そして去年のコロナパンデミックが、百貨店苦境への「追い打ち= ブースター」となったのだ。この前提を受け、ここからが本紙本欄の本題だ。
今デパートが挑むべきビジネスモデルの転換

繰り返し申し上げるが百貨店マーケットの縮小はコロナにより加速している。本紙読者諸氏には、今まで何度もお伝えしているので「耳タコ」かもしれないが、全国百貨店の売上は1991年の9・7 兆円をピークに年々減少傾向にあり、2016年には6兆円を割り込む水準まで低下した。それでも近年(言うまでもなく2019年まで)は、都心店舗を中心にインバウンド消費や富裕層消費が活発なこともあり、大手百貨店は堅調であった。
一方、人口減少を背景に、地方店の厳しさは加速し、都心と地方の格差は一層拡大する傾向にあった。更に、2020年はコロナ禍が直撃したことにより、これまでの牽引役であったインバウンドが一気に蒸発するとともに、国内消費についても 緊急事態宣言発出により2ヶ月近くにわたり休業を余儀なくされたことや、その後も感染リスク回避による外出自粛など、人流抑制策を継続した影響により4・2兆円まで落ち込むこととなった。
百貨店マーケットの縮小は、人口減少や二極化の進行による中間層の崩壊、さらにはEコマースの急拡大をはじめとする業際を越えた競争激化などの外部要因もあるが、それ以上に本質的な課題は、お客様の変化に対応しきれていない(デパートという)ビジネスモデルの「陳腐化」にあると言って良いだろう。コロナ禍を契機として、多くのコトがリセットされ、10
年分の変化が一気に押し寄せたからだ。
百貨店はここで自らを変革できなければ、市場からだけでなく史上からも退場を迫られる大転換点を迎えているのだ。
デパートの生い立ち
百貨店というビジネスモデルが誕生したのは遡ること約100年前。
その名は紳士・婦人の洋服から呉服、子供服・玩具 、家具・家電、食品まで、あらゆる商品を取り扱っていたことに由来している。事業構造では、かつては仕入れて売るという、在庫リスクを取った買取りが主流だった。それが80年代には在庫を持たない消化仕入がおよそ8割にまで拡大し、ビジネスの中心はマーチャンダイジングからマーケティングへとシフトしていった。それらと同時に、百貨店という名の由来とも言えるフルラインの品揃えではなく、DCブランドブームを背景とした衣料品、特に婦人服に過度に依存した店づくりを進めたのだ。
後から検証すれば「功罪相半ば」ではあるものの、まさに百貨店業界が売上のピークを迎えた時代でもあった。
一方、ちょうどその頃を境に日本の消費支出の中身は急速に変化していく。総務省の家計支出調査によれば、91年に7.3% を占めていた被服履物への支出は、2019年には3・7%と 半分近くにまで低下した。しかしながら、百貨店はかつての成功体験から中々抜け出すことができず、婦人服に過剰に面積配分した状況が続いたことにより、ますますお客様の嗜好や購買行動とのズレが生じることとなった。
ここに至り、百貨店が提供するコンテンツと、時代のニーズとのミスマッチ解消には抜本的な構造変革が不可欠な状況となった。
復習ここまでとし、ここからは、いち早く時代対応に着手した、Jフロントリテイリングを見てみよう。
新たなビジネスモデルの模索「脱百貨店」
Jフロントリテイリングは新たな百貨店ビジネスモデルとして、大きく2つの方向性で変革を図ることとしている。
ひとつは、「百貨店をやらない」という選択肢だ。それは、不動産賃貸ビジネスに100%転換するということだ。
2017年に旧松坂屋銀座店跡地を含む2街区一体開発により誕生したGINZASIXが、まさにこれにあたる。
もうひとつは、百貨店ブランドの元で不動産賃貸と買取り・消化仕入をミックスした「ハイブリッド型モデル」を構築することだ。2019年に開業した大丸心斎橋店新本館がその代表例だ。
いままで百貨店が続けてきた消化仕入れの利点は、売上成長を実現することで、より大きなリターンを追求できることであり、一方で不動産賃貸ビジネスにおける「定期賃貸借」の利点は、安定した収益の獲得や、運営コストの圧縮を実現することだ。更に、サービス消費、体験型消費への対応強化に向け、テナントバリエーションを拡大することで店頭の鮮度アップを図れることも大きい。
もちろんこれには、店舗ごとに顧客ターゲットやエリア特性、建物形態などを考慮し、最適なバランスを導き出すことが重要なことはいうまでもない。
店づくりにおいてもう一つ重要なこと
二つと言ったが三つ目の変革は「サステナビリティ」の視点だ。Jフロントは、脱炭素社会の実現に貢献するため、店舗環境の見直しを推進している。
2019年度に建替えが完了した大丸心斎橋店は、館内で使用する電力を100%再生可能エネルギーに切り替えた。
また、グループ傘下の渋谷PARCOは国土交通省から「サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)」として採択された。Jフロントは、今後もこうした取り組みを他の店舗にも拡大する、としている。
サステナビリティは、業種を問わず、今後重要度が増していくテーマである。本欄でも今後度々取り上げることになるだろう。
リアルとデジタルを融合した進化形
既存のリアル店舗は、こうした方向でビジネスモデルを変革していくが今般のコロナ禍で明らかになったのは、リアル店舗を中心としたビジネスがいかに「時間と場所」に制約されたものであるかということだ。この課題を克服していくためには、デジタル対応が不可欠であることは言うまでもない。しかし、我々( 百貨店) の主戦場はあくまでも人と人とのコミュニケーションを通じて提供価値を増幅していくことであり、そこに強みがある。デジタル活用によりフルアイテムでEコマースを拡大していく方向ではない。起点はあくまでリアル店舗で展開するコンテンツと、独自の編集力に基づく世界感を創出することだ。
「リアル店舗に一層磨きをかけるとともに、そこにデジタルを融合させることにより、人を中心とした独自のメディアを構築し、時間と場所の制約を克服することに挑戦する」と聞くと、いかにも百貨店広報部の「模範解答的キャッチフレーズ」に聞こえる。もちろんそれは、間違ってはいない。問題はその課題を「有言実行」できるかだ。これにより、Jフロントは収益を複線化し 「メディアコマース」へと進化させる、としている。
合言葉はECシフト
どの百貨店も、富裕層シフトとともに、EC強化、デジタルシフトという目標を掲げて久しい。失礼、久しいと言っても、ここ5~6年のことであるが。
百貨店が発信する情報の中には、オンライン接客、ZOOMの活用、VR(仮想現実)店舗、という先進的なコトバが踊る。しかし我々門外漢には、ネット上の出来事は、仮想空間だけに「空虚」に感じる、と言ったら、言い過ぎだろうか?そう言った新しい販売(顧客から見れば購買)手法を、活用している方がどれだけ居るのだろうか。
判らないままで済ませてはいけない。まずはEC(Eコマース)の勉強から始めよう。「電子商取引」よりも「ネットショッピング」の方が判りやすいだろう。
EC拡大の前提となる消費者の心理、行動を探るため、次にアンケート調査を検証しよう。
ソフトバンクの子会社が「コロナ禍における新たなEC消費・行動変容に関する調査」を実施した。オンラインでの買い物の利用頻度、購入アイテム、年間購入金額、決済手段などを調査した。( 7 ~ 8 月にインターネットで調査。対象は10~90代の男女3600人)
ネットショッピングの隆盛
オンラインで買い物・サービス利用をする頻度はコロナ禍でも「変わらない」と回答した人は57・3%と半数を超え、「増えた」34・5%、「減った」4・8%となった。年代別では10代女性の6割、10代男性と20~30代女性の4割以上が「増えた」と回答しており、特に若い世代でEC利用の頻度が増加していることがわかった。言うまでもなく、百貨店のメイン客層はミドル~シニアの女性であるから、一見影響は小さく思えるかもしれないが、10年後20年後の客数の先細りは明らかだ。
新たにオンラインで購入するようになったアイテムについての質問では「ファッション・インナー・ファッション小物」21%、「食品・スイーツ・ソフトドリンク」20%、「家電・パソコン・通信機器」17・2%となった。
百貨店への影響が小さい訳はない。
コロナ前(2019年度)とコロナ下(2020年度)のオンラインでの年間購入金額は、コロナ前は「1万円未満」が15・2%だったのに対し、コロナ下では9・9%に減り、1万円以上の全ての項目でコロナ前の1年間と比較して割合が高くなった。購入頻度が高まった上にEC利用金額も増加傾向にある。
オンラインでの買い物・サービス利用で最も利用している決済手段は、「クレジットカード」が64・1%と圧倒し、続くペイペイが7・6%、コンビニエンスストア決済が3・8%という結果だった。
ソフトバンク系の調査だからペイペイがクローズアップされているのではないだろうが・・
これらの結果から、2020年から続く新型コロナウイルスの影響で、「様々な商品やサービスにおいて消費者のオンライン購入・利用の需要が高まっている」としている。
ECの隆盛を支える「宅配ビジネス」
ECを支える両輪のもう一つは、ヤマトや佐川といった物流大手だ。もちろん日本郵政を含め、この業界は3社の寡占状態だ。
コロナ禍からの企業業績の回復は、勝ち組と負け組の格差が拡大して「K字型」に引き裂かれていくという二極化の議論が盛んだ。では次に、物流業界の主要企業が置かれた状況を、日本郵政、SGホールディングス( 佐川急便)、ヤマトホールディングスの3社の決算から見て行こう。
決算データを基に「直近四半期の業績」に焦点を当て、前年同期比で増収率を算出した。対象期間は2021年4~6月の直近四半期としている。各社の増収率は以下の通りだ。物流3社は全て前年同期比増収となった。
日本郵政
増収率:2・5%(四半期の経常収益2兆8641億円)
SGホールディングス
増収率:9・4%(四半期の営業収益3475億円)
ヤマトホールディングス
増収率:7・1%(四半期の営業収益4198億円)
佐川増収の要因は
コロナ禍でEC利用がより活発化し、物流業界のビジネスの需要は拡大。物流3社の四半期増収率は全てプラスとなった。そんな中、最も高い増収率を記録したのはSGホールディングス(佐川急便)だ。増収率No.1の背景にある「巣ごもり」以外の要因とは何なのか。
2022年3月期第1四半期の営業収益を事業セグメント別に見てみよう。
まず、主力のデリバリー事業(飛脚便やメール便) が営業収益2544億円(前年同期比4・6%増)と、前年同期を上回った。昨年から続くコロナ禍の巣ごもり需要で個人消費者のEC利用が活発であることに加えて、BtoB領域での荷物の受託も進んだのだ。
主要な商品の取扱い個数は3億4700万個(同1・5%増)と前年同期の数を上回っている。
また、ロジスティクス事業は営業収益771億円(同89・1%増)と、大幅増収だった。これに関しては、コンテナ不足の中で既存顧客の輸送物量の増加に対応できたことや、海外輸送の新規案件を受注したことなどが増収につながった、という。
3ヶ月で3・5億個の荷物とは驚きだ。佐川だけで月に1億個を超えているのだ。我々が黒猫や飛脚のトラックを目にする度に、その分デパート来店者数が減っている、と考えるのは、年寄の被害妄想の域なのだろうか。
百貨店のコンペティターはアマゾン
ここ5年くらい、こう言われ続けている。
元々デパートの顧客であったか、そうでなかったかを問わず、コロナ禍ではほぼ誰もがECやデリバリーを利用した。
コロナ前から「変わらず」利用している人も居るだろうし、コロナを契機として「宅配」を頼み始めた人も居るだろう。いずれにせよ、百貨店顧客が、ショッピングの選択肢として、ECという手段を認識し、それを利用し始めてしまったのだ。
近所のコンビニならともかく、百貨店は元々「わざわざ訪れる場所」である。それが「わざわざ家から行かなくても大丈夫」な購買手段を知ってしまったのだ。デパートと飲食の関係者は「ステイホーム」を疎ましく 思っているはずだ。
ECを専業とするアマゾンや宅配業者(佐川、ヤマト)は、我が世の春を謳歌している。そして彼らの時代は、つい最近始まったばかりなのだ。
結局最後は顧客とのコミュニケーション
ECは長らく主流であった「店舗での販売」という常識=「ショッピングの潮流」を変えてしまった様に見える。岐路に立った百貨店もまた、ECという新たな流れに加わろうとしている。
それは正に、己の生き残りをかけた選択であり、一編集者に、その「良し悪し」を云々する資格はない。但し、今一度、本欄冒頭のタイトルを読み返して欲しい。筆者は確かに「デパートのルネッサンスには変革が不可欠」と言った。しかしそれは、アマゾンや楽天といった先駆者が、既にメインストリームを形成している、ネットショッピングという流れに「加われ、付いて行け」ということではない。
小売の王者と呼ばれた百貨店には、顧客から支持されるブランド価値があったはずだ。デパートマンは常に、商品知識を蓄え、接客手法を磨き、顧客の「欲しいモノ」と「通いたくなる場」を設えていたはずだ。三越伊勢丹や大丸松坂屋は、そのノウハウを「ネットを通じて」顧客に提供できる、と言い切れるのだろうか。
アマゾン信者 = ネット購買者は、既に「時短とコスパ」という2つのメダルを手にしている。
デパートは、その彼ら、彼女らに、「時間と手間」をかけて貰い、その代わりに、価格以上の価値を提供しなければならないのだ。その価値とは、例えばそのアイテムのこだわりやストーリーかもしれないし、百貨店で買うことのステイタスなのかもしれない。
結局は、顧客といかに生きたコミュニケーションをとるかが決め手になるのだ。デパートはそんな目に見えない「付加価値」という剣で、アマゾンというモンスターと戦うのだ。
「リアル店舗に一層磨きをかけるとともに、そこにデジタルを融合させる」とは先のJ フロントの言だが、「二兎を追う者は一兎をも得ず」にならなければと願う。筆者はもちろんデパートの味方であり、応援もし ている。例えそれが判官贔屓であったとしても。

デパート新聞編集長
連載 デパートのルネッサンスはどこにある?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月15 日号-第130回 池袋西武の初売りに行ってきた。脱デパートは非デパートなのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月01 日号-第129回 ジャパニーズホラー再考
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月15 日号-第128回 新宿伊勢丹に学ぶ
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月01 日号-第127回「モノ消費からコト消費」のその先は
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月15 日号-第126回 お化け屋敷はデパートの救世主なのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月01 日号-第125回 デパートを巡る様々なニュース 後追い記事の後を追う
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月15 日号-第124回 百貨店の閉店で街は寂れたのか?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月01 日号-第123回 池袋西武の現在位置 ―代表と店長と―
- ヨドバシカメラの素質と資質
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年9月15 日号-第122 回 インバウンドバブルの終焉?