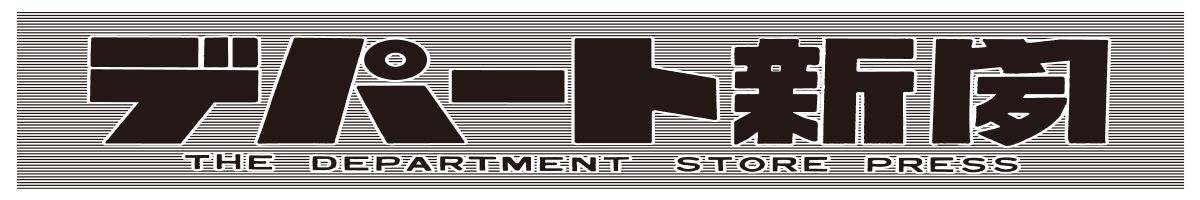デパートのルネッサンスはどこにある? 2020年11月15日号-13
地方百貨店の反転攻勢
存在感増す地方百貨店
福島県郡山市の「うすい百貨店」は県内唯一の百貨店である。賢明なる読者諸氏には、言及不要かとは思うが、山形県や徳島県には、もはや百貨店は存在しない。「デパート消滅都市」とか「百貨店空白県」などと呼ばれるこの現象は、今年に入ってから顕在化した。
レナウンの再生断念(破産)のニュースに象徴されるが、今更ながら国内のファッション需要の低迷=百貨店アパレルの衰退を実感した。これも繰り返しになって恐縮だが、これはコロナ禍による災厄というより、コロナがきっかけとなり、更に衰退が加速した、というのが実態だ。
話を戻そう。
うすい百貨店は、地域のニーズに対応した営業施策により、店舗への集客に力を入れている、知る人ぞ知る、地方百貨店の優等生だ。本紙では何度も触れているが、コロナの非常事態宣言解除後に、いち早く立ち直ったのは、地方のデパートや郊外の商業施設だった。その中でも「うすい」は、6月売上を前年同月比5%減に止め、その後の7、8月は外出自粛明けの反動増により、ともに前年実績を上回った。顧客が「安心できる近所で」買物をしようという、消費傾向が後押ししたのだ。
もちろん、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う営業自粛により、4月8日から時短営業、同23日からは食品を除き休業を余儀なくされた。しかし、半月足らずの5月8日からは、いち早く時短営業を再開した。通常営業に戻った6月以降は、前述の通りだ。郡山の地方デパートと、感染者数増により長期休業を強いられた、都心の大手百貨店を、単純比較するのは酷だが、実態として休業期間は短かったのだ。
7、8月に売上がプラスに転じた要因は、ラグジュアリーブランドが前1G年並みまで回復したことと、「巣ごもり消費」と呼ばれる自家需要の伸びを反映し、生鮮食料品、寝具、書籍等が高稼働したためだ。いずれも「家で快適に過ごす」ためのアイテムであり、ニトリや無印良品の好調と、同じモチベーションに支えられた消費と言える。
更に驚くべきは中元商戦だ。何と前年並みの売上を確保したのだ。これも、いつまでもコロナの新規感染者数が下げ止まらない都心とは、事情が異なることは言うまでもないが、近隣の顧客に支えられている、地方デパートの強みを、遺憾なく発揮した結果だ。
とは言え、地方百貨店の優等生であっても、コロナ禍で無傷でいられたわけではない。衣料品の売上げは20年度上期(2~7月)で30%減った。卒業式や入学式といったイベントの中止により、オケージョン需要が50%マイナスだったほか、付随する主力のミセスゾーンの苦戦も大きい。NB(ナショナルブランド)を中心に、婦人服、紳士服、子供服の不振が続き、今年に入り30店舗近いショップ(ブランド)が退店した。
福島中合と郡山うすい
本紙では何度も言及しているが、百貨店はうすいに限らず、衣料品偏重からの脱却を進めなければ後がない状況が続く。更にアパレルが減った売場を、飲食・健康・遊び・学び、といった時間消費型売場へ=コト消費へシフトすることが、百貨店のサバイバルにとっては最も重要だ。
県内の同業者である、福島市の「中合」が8月31日で閉店した。これに伴い、うすいは福島出張所を開設、県北エリアの外商の拠点とした。11月にはこの出張所を2倍の40坪規模に拡張し、学校制服の受注窓口にする。手回し良く(失礼、他意はない)すでに中合の外商担当者を社員として再雇用しており、中合の顧客の囲い込み(うすいにとっては新規開拓である)も、進めている。
これは、県内でのシェア争いに勝ったとか、残存者利益にありついたとか、そう言った問題ではない。そもそも県庁所在地である福島市の人口28万人に対し、郡山市は33万人であり、人口密度も郡山市の方が高い。福島県に限らず、昔から政治経済と商業(繁華街)の中心が異なる事例には事欠かない。脱線ついでに言うと、「福島県庁を郡山に移転推進する会」というものまである。
本紙4月15日号で特集した、大沼百貨店の破綻の記事を思い返して欲しい。山形県山形市民は、大事な買物は越境して「東北の中心都市」である仙台市まで出掛けており、大沼破綻の原因の一つにも挙げられていた。福島市の中合百貨店の閉店も、福島市民の仙台遠征が、少なからず影響していることは否めない。福島市は県の最北端に位置し、山形市は県の南東に位置し、同じように宮城県に接している。マイカーだけでなく、直行バスの存在も大きいと聞いた。
郡山市が、県央に位置し、仙台商圏の影響を受けない「独立商圏」を形成していたことが、福島市の中合との差であったのは事実だ。だが、地方百貨店のサバイバルは、例え立地と商圏が揃っていても容易ではない。本紙社主の論説でも取り上げているが、最も大事な要素の一つが地元顧客とのコミュニケーションだ。
地元の財界や商店街、顧客らがまとまって、7月に「うすいファンクラブ」を発足させた。単独の商業施設である百貨店に対して、民間有志のファンクラブの結成は全国でも珍しい例と言える。創業350年の歴史に加え、地元の応援団に背中を押され、地域密着の商売を更に深化させる方針だという。
そのうすいも、残念ながら、今期は最終赤字に転じる見通しだ。しかし2019年まで12年連続で黒字を確保していたうすいは、(正に地方百貨店の優等生だが)来期には最終損益で再び黒字化を目指すという。今現在、地域との「繋がり」が見えており、この後の5年10年先の商売も、きっと見通せているに違いない。
東北の百貨店事情
東北の百貨店の中では、2019年の売上高が全国38位であった藤崎百貨店( 仙台市:447億)は、別格の東北NO.1だ。もちろん大手3強の一角を占める全国57位の仙台三越(323億)も地方独立系ではないので除外して考える。それ以外で全国100位以内にランクインするのは、87位の川徳(パルクアベニューカワトク 盛岡:176億)と99位のうすい百貨店(郡山:149億)だけとなる。
南東北の3県に絞って考えると、前述した山形(大沼)、福島(中合)は、東北6県の中心でもある、大都市仙台の集客力に、対抗しきれずに閉店した形だ。地図を眺めていると、県庁所在地である山形と福島が、いかに仙台に至近であるかが判る。
あまり良い例ではないが、千葉、埼玉の人間は東京(というより銀座や新宿)のデパートに、距離や移動時間に係わらず通っている。一都三県とは呼ぶが、横浜を擁する神奈川は、当然除外している。品揃えやブランドの魅力に加え、自身のステータス(自己顕示欲と意訳すると叱責を受けるが)を満足させる「何か」が、大都市東京にはあるのだろう。
だから、山形市と福島市の住民が、仙台にショッピング遠征したからといって、郷土愛が欠落していたわけではない。仙台や東京には、人々が買物をしたくなる、ステージが用意されていたのだ。
買物というのは、金銭を対価として、モノを手に入れるだけ、ではない。わざわざ足を運び、商品を吟味し、販売員とやりとりをする、それらすべての行為が、ショッピングというひとつのレジャーなのだ。今、ECやネット通販と呼ばれる、リアル店舗を介さない買物が、コロナ禍を背景として隆盛を極めていることは、もちろん否定しない。しかし、「買物の楽しみ」を感じる消費者が居る限り、百貨店を頂点とした、小売業は滅びないはずだ。
むしろ、「楽しい買物」の提供という自らのレーゾンデートルを忘れ、アマゾンや楽天やメルカリの「ものまね」に終始する様になった時が、デパートの、そしてデパート業界の、本当の終焉であろう。
そういった意味でも、郡山のうすいも、盛岡のカワトクも、その他地方で奮闘する独立系百貨店のすべてに、地域との繋がりを更に強め、EC・通販や大都市に対抗して、ウィズコロナ時代を生き抜いて欲しい。
あなた達地方百貨店を応援するのは、本紙デパート新聞だけではない。うすい百貨店を応援するファンクラブの様に、その地域での顧客を「仲間」に進化させる取り組みが求められているのだ。そのためにデパートは、単なる「買物をする場所」以上の存在、例えば地域文化の育成を担う、ランドマークとしての役割を果たさなければならない。
もちろん簡単なことではないだろう、だが、地方百貨店はその長い歴史の中で、戦争や天災をいくつも乗り越えて来た。コロナも決して例外ではない。微力ながら本紙も、ペンを使っての協力は惜しまない。そして地方百貨店の健闘を祈る。

デパート新聞編集長
連載 デパートのルネッサンスはどこにある?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月15 日号-第130回 池袋西武の初売りに行ってきた。脱デパートは非デパートなのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月01 日号-第129回 ジャパニーズホラー再考
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月15 日号-第128回 新宿伊勢丹に学ぶ
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月01 日号-第127回「モノ消費からコト消費」のその先は
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月15 日号-第126回 お化け屋敷はデパートの救世主なのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月01 日号-第125回 デパートを巡る様々なニュース 後追い記事の後を追う
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月15 日号-第124回 百貨店の閉店で街は寂れたのか?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月01 日号-第123回 池袋西武の現在位置 ―代表と店長と―
- ヨドバシカメラの素質と資質
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年9月15 日号-第122 回 インバウンドバブルの終焉?