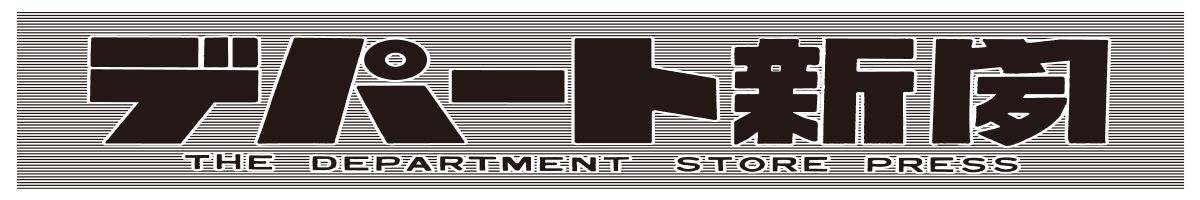デパートのルネッサンスはどこにある? 2021年05月15日号-25
コロナ禍の1年 百貨店の今
我が百貨店( 小売) 業界も、この1年、飲食や観光業界ほどではないにしろ、コロナ禍により、大きな痛手を負っている。
百貨店と商業施設の休業を伴う、3回目の緊急事態宣言は、当初5月11日まで、とされていたが、本紙が発行される5月15日を待たずに、5月末までの延長が決定した。
念のため、ここで「おさらい」をしておこう。
緊急事態宣言の期間
1回目: 2020年4月7日~5月25日
期間: 1ヶ月半余り
2回目: 2021年1月8日~3月21日
期間: 2ヶ月半
3回目: 同年4月25日~5月11日 → 5月末日まで延長
期間: 半月→1ヶ月余り
※いずれも延長期間含む〈髙島屋と大丸松坂屋〉
コロナ禍に明け暮れた2020年度、髙島屋は17年ぶり、大丸松坂屋を擁するJ.フロントリテイリングは( 松坂屋との統合前の大丸単体の赤字以来の)19年ぶりの最終赤字となった。
新型コロナウイルスの感染拡大、とりわけ昨年春( 2 0 2 0 年4 ~ 5月) の緊急事態宣言による臨時休業は、2社の2021年2月期決算に多大な影響を与えた。
髙島屋は、連結営業収益が前年同期比25・9%減の6808億円、営業赤字は134億円、最終赤字は339億円。
国際会計基準を導入しているJ.フロントは、総額売上高が前年同期比32・4%減の7662億円、営業赤字(その他営業収益、費用を含む)は242億円、最終赤字は261億円だった。
昨年初めの中国での感染拡大により、インバウンド需要が「消失」した後、店舗の営業自体を止めざるを得なかったのだから、当然の結果と言える。その後再開しても、第2波、3波が襲い、客足は従来のレベルまで戻ることはなかった。「以前の日常」には程遠い。
今、コロナは変異株が広がりを見せ、特に2社が主要店舗を持つ関西地方の状況は、とりわけ深刻だ。高齢者へのワクチン接種は今月ようやく始まったが、医療従事者への優先接種の終わりも見えない中で、泥縄式なスタートとなり、一般国民の接種はなかなか見通せない。
三越伊勢丹
そんな中で、大手百貨店のトップは、企業存続のために、いったい何を考えているのだろう。地方店舗の再生で実績を上げ、三越伊勢丹HDSのトップとなった細谷敏幸新社長の企業を存続させるためのテーマは「富裕層シフト」だと言う。
トップ交代の意義
2021年2月に三越伊勢丹HDSは、杉江俊彦前社長から細谷敏幸新社長への交代会見を行った。
百貨店業界首位の三越伊勢丹が4月1日、子会社である福岡の岩田屋三越社長であった細谷敏幸氏を、日本一の百貨店の社長に抜擢した。2月末の会見で新社長は「既存のビジネスモデルは、もはや市場に受け入れられていない」と、三越伊勢丹だけでなく、百貨店全体が直面する経営環境の厳しさを率直に語った。
三越伊勢丹の2021年3月期業績は、売上高が前期比28・5 % 減の8000億円、最終損益が450億円の赤字になる見通しだ。
売り上げがほぼ同規模のJ.フロントリテイリング(最終赤字予想186億円)と比べても、百貨店事業の売上比率が9割と突出する三越伊勢丹は、百貨店業の赤字が大きく( 第3四半期の累計で219億円の営業赤字)、大手の中でも苦境ぶりが目立つ。
賢明なる読者諸氏には「耳タコ」で恐縮だが、この苦境はコロナ禍だけが原因ではない。主力としてきた衣料品の不振、顧客の高齢化、EC(ネット通販)の台頭とその対応への出遅れなど、百貨店事業の構造的な問題に起因する部分が大きい。
その中でも大きな経営課題になっているのが、中間層の百貨店離れだ。近年はショッピングセンターや大型専門店などに中間層の足が向かっている。百貨店は今後も来店客数の大幅な増加を期待できず、1人当たりの購入額をいかに伸ばすか、各社は頭を悩ませている。
富裕層へのシフト
細谷新社長は、この課題への回答は「外商顧客ら『富裕層』に経営資源を集中させる」ことだと明言した。
「今まで百貨店はその恵まれた立地を生かし、マス( 大衆) を対象にして、とにかく店舗にお客を集めれば勝ちだった。これからはマスから個への転換を進める。」という。外商顧客へ、より多くのお金と人を投入していくということだ。細谷新社長は自ら「受け入れられていない」という百貨店のビジネスモデルについてそう述べた。つまり、中間層を含めた幅広い層から、上客向けの特別なサービスである「外商」を利用する顧客や、比較的購入単価が高い「富裕層」に、経営資源をシフトさせるというわけだ。
三越は分厚い富裕層の顧客基盤を伝統的に持っている。また伊勢丹も新宿本店を中心に年間購入額1000万円以上の顧客を多く抱えている。顧客の高齢化が進む中で、IT起業家や投資家といった「ニューリッチ」と言われる若年富裕層に大きな商機を見出しており、新たな成長の柱に据えていきたい考えだ。
実はこうした戦略は諸刃の剣であり、「置いてけぼり」となった一般消費者( マス=大衆) から、反感を買う恐れもある。ある百貨店関係者は、「貧困層への配慮など、いわゆるSDGs(持続可能な開発目標)が注目されている今、『富裕層をターゲットにします』とは、はっきりとは言いにくい面がある」と打ち明ける。
ただ、コロナ禍で逆風が吹く中、富裕層向けビジネスは一筋の光明であることは間違いない。中間層向けの衣料品販売が、ユニクロ等の台頭により大幅減になる反面、高級ブランドや宝飾・時計など、富裕層による高額品の消費はコロナ禍の現在でも絶好調だ。コロナ後の消費回復を見据えた時に、百貨店利用の中間層がしぼむ中で、富裕層ビジネスを強化するのは必然だ。
地方店のリストラ
こうした富裕層向けビジネスの強化は、慢性的な低収益体質が業績の足を引っ張る地方店の再生においても重要なカギを握る。
三越伊勢丹HDSの2020年3月期決算では、首都圏以外の地方店舗を運営する事業子会社10社のうち6社が営業赤字。コロナ禍の2021年3月期はさらに赤字が膨らみそうだ。東京の旗艦3店(伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店、三越銀座店)に収益が偏在しており、地方店の黒字化が喫緊の課題になっている。
2017年に就任した杉江俊彦社長の下では、伊勢丹松戸店や府中店、新潟三越など地方都市や大都市郊外の不採算店を相次いで閉鎖した。店舗閉鎖による退職や新規採用の抑制などを進め、2017年度末に1万4200人いた従業員を2年間で約1800人減らした。
細谷新社長は「今の時点で単純に閉店するということは、いっさい考えていない。従業員の削減も考えていない」と社長交代会見でそう断言し、追加の閉店には否定的だ。だが、業績の早期改善が実現できなければ再度のリストラは必至となる。
岩田屋( 伊勢丹) と福岡三越を運営する岩田屋三越の社長に細谷氏が就任したのは2018年4月。その1 年後の2019年3月期決算では営業利益を前期比で78%増にしたのだ。社長候補のうち、地方店再生の手腕では圧倒的にナンバーワンだった細谷氏に白羽の矢が立ったのも、こうした地方店再生の実績があるからこそだと言える。
ダウンサイジング
この業績改善に貢献した一例が、不振だった岩田屋久留米店の再建だ。日常の買い物は久留米店でしてもらい、高額品を購入する富裕層顧客には福岡市の岩田屋本店で手厚く対応するなど、本支店の連携を強化。その結果、外商の売上が拡大して収益を押し上げた。
リストラにより「守り」を強いられた杉江前社長に対し、細谷新社長率いる次期体制では、この手法が地方店再生のカギとなりそうだ。ただ、地方店では来店客が減り続け、現実として、アパレル大手や高級ブランドの撤退が進んでいる。そうなると売場の維持は難しい。
そこで三越伊勢丹が推し進めるのが地方店のダウンサイジングだ。
※これは前号で、アメリカのブルーミングデールズを例にして触れた。先ず、一部の地方店舗の売場面積を最大で従来比10分の1程度に縮小し、この小型店では店頭の品揃えを大幅に絞る。一方で店内に「デジタルサロン」を設置し、伊勢丹新宿店など、東京の旗艦店舗に顧客をオンラインでつないで、高額商品を中心に接客を受けてもらうというものだ。
2020年8月に閉店したそごう徳島店が入っていたビルへの出店を検討するなど、百貨店の「空白県」への進出ももくろむ。各地方には医師や企業経営者などの底堅い富裕層が存在する。ITを活用すれば、地方店舗にかかる固定費を大幅に圧縮しつつ、新たに富裕層を取り込めると見込んでいるのだ。
杉江前体制は、店舗閉鎖などのリストラに追われ、「守りの経営」を強いられた4年間だった。富裕層ビジネスの強化だけでなく、EC事業の売り上げ増や、競合他社に比べて出遅れ気味の不動産事業の加速など、細谷新体制を待ち受ける課題は山積している。
三越伊勢丹HDは今年5月に3カ年の新中期計画を発表する。「攻めの経営」への転換に向けて、いかに実効性のある施策を打ち出せるかがポイントになりそうだ。
最後に、直近4月の大手百貨店の近況を記す。百貨店売上高、コロナ前比20~30%マイナス
大手百貨店4社が6日発表した4月の既存店売上高( 速報値) は、新型コロナウイルス流行前の2019年同月と比べておおよそ2~3割減少した。今年4月25日に4都府県で発令された緊急事態宣言を受け、対象地域にある店舗において、一部売場を除いて臨時休業していることが響いた。三越伊勢丹ホールディングスとそごう・西武は約20%減。高島屋は26・2%減で、大丸や松坂屋を運営するJ.フロント リテイリングは約30%の減だった。緊急事態宣言の延長が決定され、今後の収益は一段と厳しい状況になる見通しだ。
詳しい数字は次号( 6月1日号) に譲るが、少なくとも5月末まで緊急事態宣言の延長が確定した今、百貨店の、そして小売の先行きは、ますます不透明となったことだけは確かだ。
休業の大義名分
今回政府と自治体は、コロナ対策の根本政策を、「酒を伴う飲食」に絞り、その前提となる「人流」の抑制を目指していた。そのために百貨店や商業施設への休業を要請した、という構図だ。丁度1年前の緊急事態宣言下での休業は、「未知のウイルス」との「初めての闘い」でもあり、百貨店側も顧客も、休業を容認した、という側面があった。
だが今回は、果たしてこれが本当に効果のある施策なのか疑問に思っている、というのが本音ではないだろうか。
食料品以外は「不要不急の業種」というレッテルを貼られ、百貨店や商業施設が営業していると「人が集まり= 感染が拡大する」という、くそみそ、失礼「十把一絡げ」の論理により、飲食店同様、社会の「休業スケープゴート」になって来た。
もし本当に「人流」を止めたければ、電車やバスといった公共交通機関をストップさせれば良い。企業に「リモートワーク」を推奨、要請するより10倍簡単な方法だ。「そんな乱暴な」と言われるかもしれないが、百貨店イコール= 不要不急のロジックこそ、相当乱暴だと、筆者は考える。不要なモノを売っていて、商売が成り立つ訳がないからだ。
百貨店が扱っているのはほぼ「生活必需品」と言っても過言ではない。例えば、政府+ 東京都が推し進める、オリンピックの聖火リレーは「不要不急」の最たるものではないか。百貨店が閉まっていて困る人はいるが、聖火リレーの中止は、いったい誰が困るのだろう。
オリンピック開催の是非について、ここでは敢えて触れないが、世界中から何万人ものアスリートとその関係者が来日すると考えると、そのリスクは計り知れない。感染力が強いとされるインドの変異ウイルスも、この国は水際で防ぐことが出来なかったのではなかったか。
5月8日、東京都の新規感染者数は再び1000人の大台を超えた。

デパート新聞編集長
連載 デパートのルネッサンスはどこにある?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年02月01 日号-第131回 「食べる本屋さん」の「ニジコミ」企画とは?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月15 日号-第130回 池袋西武の初売りに行ってきた。脱デパートは非デパートなのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月01 日号-第129回 ジャパニーズホラー再考
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月15 日号-第128回 新宿伊勢丹に学ぶ
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月01 日号-第127回「モノ消費からコト消費」のその先は
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月15 日号-第126回 お化け屋敷はデパートの救世主なのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月01 日号-第125回 デパートを巡る様々なニュース 後追い記事の後を追う
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月15 日号-第124回 百貨店の閉店で街は寂れたのか?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月01 日号-第123回 池袋西武の現在位置 ―代表と店長と―
- ヨドバシカメラの素質と資質