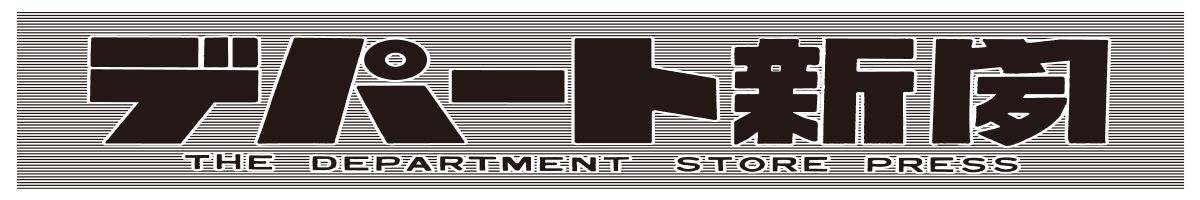デパートのルネッサンスはどこにある? 2024年12月01日号-104 セブン&アイはなぜ非上場化を目指すのか?

社会に求められる三方良しの公益資本主義
本コラムで10月に取り上げた「セブン&アイの内憂外患」つまり外資によるセブン&アイ・ホールディングスに対する買収提案の続報から見て行こう。
セブン&アイHD 創業家からの提案受け非上場化を検討
11月13日、カナダのコンビニ大手「クシュタール」から買収提案を受けているセブン&アイHDは、イトーヨーカドーの創業家が関わる企業からの提案を受けて、非上場化を検討している、というニュースが伝えられた。
8月19日、セブン&アイは、前述の「アリマンタシォン・クシュタール」から7兆円規模の買収提案を受けたことを明かし、「同社の提案を受けない」という判断を示していた。
こうした中、11月13日になって、傘下のスーパー「イトーヨーカ堂」を設立した資産管理会社である「伊藤興業」などから新たな提案を受けたと発表した。伊藤の名から判るが、この創業家一族による資産管理会社は、セブン&アイの株式の8%余りを保有している、という。
対抗策
関係者によると、創業家側の提案はセブン&アイの株式を買収し非上場化するMBO=マネジメント・バイアウトと呼ばれるものだということで、今後、クシュタール社が敵対的な買収に踏み切った際の対抗策として備える狙いがあるとみられる。
用語解説:
MBOとは「Management Buyout(マネジメント・バイアウト)」の略で、M&Aの手法の一つ。MBOは「経営陣による買収」などと訳され、企業の経営陣が株式や一部の事業部門を買い取ることを通じて経営権を取得することを示す。
一方で、セブン&アイの時価総額は6兆円規模で、創業家主導の買収には多額の資金が必要なことから、創業家は複数の金融機関などと協議を始めているという。
セブン&アイは「潜在的な株主価値の実現のためのすべての選択肢を客観的に検討しております」とコメントしていて、今回の提案を社外取締役のみで構成される特別委員会で検討するとしている。
買収提案
カナダのコンビニ大手「アリマンタシォン・クシュタール」によるセブン&アイ・ホールディングスへの買収提案が明らかになったのは今年8月。
390億ドル、現在の為替レートで(1ドル=155円)およそ6兆円でグループ全体を買収するというものだった。
これに対し、セブン&アイは9月上旬、社外取締役のみで構成される特別委員会でこの提案を検討し、「当社の価値を著しく過小評価している」として、提案を受け入れられないとする内容の書簡をクシュタール社に送ったのは、ご存知の通りだ。
しかし10月上旬、クシュタール社が買収金額をこれまでの提案から2割程度増額し、7兆円規模に引き上げる新たな提案を行ったことが判り、セブン&アイの井阪社長は、先月開いた会見で、「真摯(しんし)に内容をお聞きして対応しようと考えている」と述べたものの、新たな提案に対する具体的な回答はなされていない。
言い方は悪いが「真摯どころか、放置したままで、防衛策に踏み切る」という結論の様だ。
MBOのメリット
MBOは、前述の様に、経営者が「事業の継続を前提として」一般株主から自社の株式を取得する、企業買収の手法の1つだ。経営者が資金の全部または一部を出資し、上場企業の株式を非上場化する手段としても使われる。
経営陣が株主となることで、株主の意向に左右されずに経営にあたることができるため、大胆な事業構造改革などに取り組めるメリットがあるとされている。
いわゆる「もの言う株主」と呼ばれるアクティビストによる上場企業への要求が強まる中、MBOを行う大手企業が相次いでいて、去年から今年にかけて大正製薬やベネッセ、それに永谷園(いずれもホールディングス)などがMBOを行ってきた。
国内では、これまで大正製薬が行った7000億円に上るMBOがもっとも規模が大きく、仮にセブン&アイのMBOが実現すれば、過去最大の事例となる。
本コラムでも「会社は誰のもの」という議論をしたことがあるが、ここまで来ると、会社は一般株主よりも創業家と経営陣を守ることを最優先しているとしか思えない。
ここで先ず、一般的な識者のご意見を紹介したい。外資によるセブン&アイの買収を「日本国の食の安全保障の問題」と捉えている。
識者の見識
『日本企業であるセブン&アイには、まず日本社会への責任がある。同社の重要な存在意義は、わが国の消費者が安心して食料や日用品を購入できるインフラを提供することだ。
道路や鉄道と同じく、スーパーやコンビニは人々の生活に欠かせないものである。社会インフラとしての小売りビジネスを、いかに安定的に継続することができるか。それが、最も重要だ。
仮に同社が海外企業に買収され、効率性を重視して国内のスーパーやコンビニを大幅に縮小することになると、消費者に多大な影響が及ぶ可能性は高い。
地方では買い物難民が増えるだろう。海外では、小売企業は経済安全保障上の重要業種との考えにより、外資による買収を認めなかったケースもある。
今後の展開の一つとして、同社が国内事業と海外事業を分離する可能性もあるだろう。いずれにしても、日本の人々が安心して買い物できる体制を整えることこそ、セブン&アイが最大の強みを発揮する唯一無二のポイントだ。』
ここで力説されている事については「正論」であり、簡単に反論はし辛いし、例え現代であっても「非国民」扱いされてしまうかもしれない。落ち着いてゆっくり考えていこう。
強欲資本主義
本コラムでは、企業は株主以外に様々なステークホルダーに配慮すべきという、ステークホルダー資本主義を紹介し、株主第一( 至上) 主義を牽制して来たつもりである。念のため。
本コラム10月1日号の「セブン&アイの内憂外患」前編を参照しよう。
用語解説:ステークホルダー資本主義
従来からの「株主資本主義(株主至上主義)」では、短期的な株主の利益の最大化が最も重要、と位置づけられており、その結果、従業員や環境、地域社会に負荷をかけるという問題が生じている。
それらの対義語として生まれたコトバであり、公益資本主義ともいう。が、事ここに至っては、井阪社長は株主ではあるものの、そのわずか8%に過ぎない「創業家」と、その傀儡である「現経営陣」を守ることしか念頭にない様だ。株主資本主義でも、株主至上主義でさえない、創業家資本主義とでも呼べば良いのであろうか。
いずれにしてもステークホルダー資本主義や公益の概念からは何万光年の彼方である。
商売の規範である「三良し」売り手良し、買い手良し、世間(社会)良し、どころか、一般株主までも置き去りにするという、正に強欲資本主義の見本の様な事例だ。
これでは、何のための株式会社か判らない。法律に触れなければ何をしても良い、金で解決すれば「文句ないでしょ」と言わんばかりの強欲の見本なのだ。
レピュテーションリスクのコトはいうまでもなく、だ。
ここで、筆者の様な「怒りに任せた」批判だけでなく、今一度専門家の話を紹介しておこう。
有効な選択肢
流通業界に詳しい証券アナリストによると、セブン&アイが非上場化を検討する狙いについて「セブン側としてはクシュタール社の提案を拒否するだけでは不充分であり、既存株主からの要求に応えるためには、新しい提案を出していく必要がある。その一つの答えが創業家による買収提案ということだと思う」と話している。
セブン&アイの時価総額は6兆円規模で、買収には多額の資金が必要だが、今回の提案について同アナリストは「有効な選択肢の一つだと思う。セブン&アイの現状のアメリカと日本のコンビニの事業基盤や今の稼ぐ力を踏まえれば、決して不可能な提案ではない。
しかし、買収を実現するにはおそらく国内のメガバンクはすべてが支援に入らないといけないことになるだろう。そのためにはどうやって企業価値を上げていくのかについて、しっかり説明責任を果たす必要がある」とも指摘している、という。
本紙のスタンス
創業家支配や現経営陣の体制を守るためだけに、「国内のメガバンクはすべてが支援に入らないといけない」というのは、筆者には正気の沙汰とは思えない。セブン&アイが、というより、井阪社長という経営者が、きちんと説明責任を果たせる人物であるかどうかは、本コラムで2年に亘り、その手法と言動を見て来たからこそ、筆者はよく判っているつもりだ。証券アナリストが「有効な選択肢の一つ」というのは理論的には可能であろうともだ。
顧客や従業員を蔑ろにし、今また株主さえも創業家や経営陣のためにその利益を後回しする人物を、日本の経済界全体が守ってあげなくてはならない義理や責任が、一体どこにあるのだろう。
前述の「食の安全保障」問題があったとしてもだ。
セブンが海外資本となったら、不採算店舗のリストラにより、近所のコンビニが閉店し、買い物難民が生まれる。等と、直ぐに外資を警戒したり、排除する意見が聞かれる。
であれば、消費者が困ろうが、従業員が路頭に迷おうが、そごう・西武を売却し、更には祖業であるイトーヨーカドーさえ大量閉店させてきたセブン&アイに、皆何を望んでいるのであろう。
地域の食を守る?
地域の消費者を守るために、利益を度外視してヨーカ堂やセブンイレブンの撤退計画を延期したり変更したりしたことが、今まであっただろうか。
百歩譲って、儲からない事業から撤退するのも、不採算店舗を閉店するのも、商売の基本のキである。それを外資がやれば悪で、創業者の伊藤家がやれば「仕方がない」では、本末転倒どころか贔屓の引き倒しだ。
迷える買い物難民たちに対し、識者や評論家は、伊藤家ならばその食卓を守ってくれるという、確たる保証でもあるのだろうか。
筆者はクシュタールによるセブン&アイの買収に諸手を上げて大賛成と言っている訳ではない。セブン&アイには、消費者と従業員と、地域の事をも考える、いわゆる「三方良し」の公益資本主義というモノを考えてみて欲しい、と言っているのだ。
他のあらゆる事業がそうである以上に「小売り」というのは市民の暮らしを支えている。そういった公共性の高い事業、商売であればあるほど、我々メディアが、場合によっては注意や警告を発し、ウォッチしていかなければならないと思うからだ。
結論
もし、セブン&アイの現経営陣が、公益性を考慮して商売を続けてくれるのであれば、国内のメガバンクすべてが、セブンの支援に入ることを、だれも反対しないであろうし、もちろん預金者の一人として、微力ながら筆者も応援に回る。
「すべての経営者よ、賢人たれ、そして聖人たれ!」とは言わないが、日本の小売り流通の覇者であるセブン&アイには、申し上げた様な高邁な使命感を持って欲しいと願ってやまない。
自分達の利益だけを優先し、目先の商売の事しか考えていない様に見える創業家や経営陣を無批判で放置していたら、日本経済の見通しは暗いからだ。

デパート新聞編集長
連載 デパートのルネッサンスはどこにある?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月15 日号-第130回 池袋西武の初売りに行ってきた。脱デパートは非デパートなのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月01 日号-第129回 ジャパニーズホラー再考
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月15 日号-第128回 新宿伊勢丹に学ぶ
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月01 日号-第127回「モノ消費からコト消費」のその先は
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月15 日号-第126回 お化け屋敷はデパートの救世主なのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月01 日号-第125回 デパートを巡る様々なニュース 後追い記事の後を追う
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月15 日号-第124回 百貨店の閉店で街は寂れたのか?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月01 日号-第123回 池袋西武の現在位置 ―代表と店長と―
- ヨドバシカメラの素質と資質
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年9月15 日号-第122 回 インバウンドバブルの終焉?