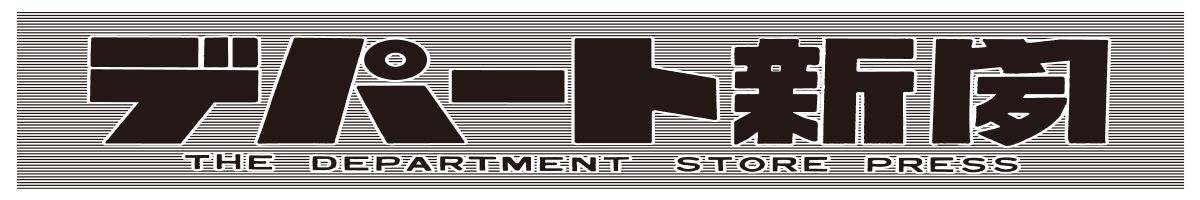デパートのルネッサンスはどこにある? 2020年09月01日号-8
岐路に立つ百貨店 <郊外進出とSC化戦略>
目次
ウィズコロナの時代
8月も中旬になり、終戦記念日が過ぎても、新規感染者数は高止まりを続けている。我々の感覚も麻痺して来ているのか、PCRの陽性者が東京で300人を超えようが、全国で1000人を超えようが、もはや誰も驚かない。特に年配者の多くは、20~30代の若者が感染者の7割を占め、ほぼ無症状というニュースに、眉をひそめたり、内心ほっとしたりするだけで、別世界の出来事と考えている。
本紙2月15日号のコラムで、新型肺炎によるインバウンド需要の減少に言及してから、早くも6ヶ月が経過している。
半年たって判ったことは、この「コロナ禍」はもはや自然に収束するものではなく、従って「アフターコロナ」でなく「ウィズコロナ」の時代が到来したということだ。
コロナ禍は、どの業界にも、少なからずマイナス影響を与えており、百貨店業界も(ごく一部の例外はあるも)4~5月の営業自粛期間には、売上と利益の大半を失った。
顧客の都心離れ
前号でも伝えたが、本紙デパート新聞は、「どうすれば百貨店は生き残ることができるのか」をミッションとしている。
8月合併号では、その生き残り策の一例として、百貨店のSC化=テナント化を考察し、例として所沢と東戸塚の西武S.C.を取り上げた。デパートというその地域の「ハレ文化の担い手」が日常化する事に、筆者が批判的な論調となったことは否定しない。もちろん、典型的な郊外型百貨店である両店にとって、テナントシェアの増大は「背に腹は代えられない」という理屈も理解できる。
コロナ禍で、中々回復の兆しが見えない都心のデパートを尻目に、郊外型の百貨店やSCは堅調だと言う。「都心は怖いが近所は安心」という心理が、顧客の支持に繋がっているのだ。日々の生活を「少しでも元に戻したい」という、人々の願いが郊外店舗の数字に反映した形だ。昨年までは、インバウンド需要の隆盛もあり「都心回帰」に踊った顧客も、手のひら返した様に、揃って「都心遺棄」に鞍替えをしたのだ。
絶対客数の減少
もちろん都心回帰する熱心な百貨店ファンも多数存在する。但し、地方も含めた老舗デパートの経営を支えている顧客の多くは高齢者だ。4年後の2024年には、第一次ベビーブーム世代全員が75才以上となるのが、日本の現実だ。
毎年150万人もの人口が減っていくこの国で、今まで通りの戦略で百貨店が生き残れる、といった楽観論は非常に危険だ。百貨店の経営者には、生き残りを賭けた事業変革に「わずか4年しかない」という危機感と、覚悟が求められているのだ。若者の減少に悩んでいた百貨店業界は、今度は高齢者の減少=絶対客数の減少という未曽有の事態に直面することとなる。
人口減少は日本社会全体の大問題である。もちろん景気の停滞どころか、後退に備える戦略は、誰も持ち合わせていない。「時間が解決してくれるさ」と、後期高齢者の皮肉とも愚痴ともとれない声だけが、聞こえてくる。
郊外でも明暗が
前述した百貨店のSC化は、郊外に限った話ではないし、今に始まった話でもない。玉川髙島屋S・Cは50年前から、百貨店と専門店(テナント)の複合業態を、(当時は正真正銘の郊外であった)二子玉川にオープンさせている。
言うまでもないが、二子玉はもはや郊外ではないし、厳密には準郊外とも呼べない。誰もが吉祥寺や白金、自由ヶ丘を高級住宅街とは認識しても、郊外とは思っていないだろう。二子玉川は、髙島屋のブランド力が、郊外の駅前を一変させた好例であろう。但し、所沢や戸塚が二子玉の様に変貌を遂げるかは未知数だ。
その髙島屋も盤石とは言い難い。
以下、本紙神奈川支局より
髙島屋港南台店36年で閉店
2020年8月16日、髙島屋港南台店(横浜市港南区)は36年間の歴史に幕を下ろした。売り場面積8214平方メートルを持つ髙島屋港南台が開店したのは、東京ディズニーランドの開園と同じ年の1983年10月。当時人気のラテンバンド「有馬徹とノーチェ・クバーナ」が華やかな演奏で開店を飾った。1984年には港南区の人口が20万人を突破、1985年つくば科学万博開催、1988年瀬戸大橋、青函トンネル開通、1989年横浜ベイブリッジ開通など多くの大型プロジェクトが続き好景気に支えられ順調に売り上げを伸ばし、ピークの1991年には180億円に達した。同店は港南区、栄区、磯子区、鎌倉市など近隣自治体の住民が地下フロアの食料品などを中心に利用してきたが、その後人口減少や高齢化などに伴い近年は売上が減少し2019年度は76億円とピーク時の半分以下にまで落ち込んでいた。
閉店に先立って行われた「さよならセール」には、入り口前で「思い出をつなぐ写真展-ともに歩んだ36年間を振り返る」が開催されじっと見入っている人たちや記念に写真を撮る夫婦も見られた。その隣に設置された「ひまわりのメッセージボード」には大勢の利用者から思い思いのコメントが寄せられていた。中には次のようなものがあった。
「日々の買い物、ちょっとした手土産、職場で着るスーツやカットソーなど色んな場面で利用させていただきました。」
「お中元、お歳暮、誕生日プレゼント、選ぶのにいつも相談に乗って下さり助かっていました。髙島屋港南台店がなくなるのは本当にイヤです。」
「母との待ち合わせ場所でした。10年前なくなった母が懇意にしていました。なくなって寂しいです。」
「思い出がたくさん、たくさんある大切な場所です。ずっとずっと在り続けてくれると当然のように思っていました。本当にありがとう。ずっと好きでした。」
「子供の頃から何度も祖父母や両親と来ました。観るだけでも珍しいものや色々心が豊かになりました。」
「子供が生まれる前から、そして成長とともにずっとお世話になりました。たくさんの思い出ありがとう。」
最後には短く「さみしいです。悪い夢であってほしい。また来てください。」
沿線のブランド化
東急電鉄も、指をくわえて見ていた訳ではない。元々「高級住宅街」であった松濤や田園調布は別格として、二子玉川や自由ヶ丘の繁栄は、半世紀以上かけて、このエリアを開発してきた東急電鉄+不動産の、経営手腕によることは論を待たない。野球場や遊園地、動物園を作って客寄せをしている、西武や東武と比較するのは野暮というものだろう。答えは、沿線の地価を見れば一目瞭然だからだ。
小田原、箱根といった、一大観光拠点を後背地とし、日本一のターミナル駅である新宿を起点とする小田急や、並走する京王も、渋谷と横浜という「お洒落な街」を結ぶ東急ブランドには、太刀打ち出来なかった。ましてや埼玉の玄関口である池袋を起点とする、西武、東武といった「田舎鉄道」では、失礼ながらブランド力で、足元にも及ばない。
東急の街「渋谷」
渋谷の東急東横店は、コロナ真っただ中の3月31日に85年の歴史を閉じた。じわじわと感染者が増加し、4月7日に全国に非常事態宣言が出される直前の閉店となった。最悪のタイミングにより、多くの顧客に惜しまれながら、という感動のシーンもなく、非常に残念な幕切れとなった。
そのうっ憤を晴らすように、東急は、本拠地渋谷で怒涛の開発ラッシュの最中だ。2014年の「ヒカリエ」(旧東急文化会館)に始まった新ビル建設は、2018年に飲食に特化した「ストリーム」と続き、2019年11月には東横線渋谷駅跡にランドマークとして47階立ての高層ビル「スクランブルスクエア」を、バスターミナルを挟んだ東急プラザ跡に「フクラス」を、相次いでオープンさせた。
撤退続く西武・そごう
西武百貨店はというと、1968年に開業し、老朽化した渋谷西武を来年建て替える、としているが、「そのまま閉店してしまうのでは」という噂が絶えない。
西武百貨店は、今や西武鉄道とはまったく無関係である。一方の東急百貨店は、親会社の鉄道と二人三脚を続けている。
そごう・西武は昨年、新たに5店舗の営業を終了すると発表した。同社は、2016年2月に西武春日部店、同年9月に西武旭川店とそごう柏店を閉店。また、2018年2月には西武船橋店と西武小田原店の営業を終了するなど、地方を中心とした店舗の再編が続いている。
西武大津店、西武岡崎店、そごう徳島店、そごう西神店は2020年8月末日、そごう川口店は2021年2月末日に閉店を予定。 今回閉店する5店舗は、いずれも営業不振が続き、業績改善が見込めなかったことから、同社は営業終了を決定。経営資源の集中を図ることで事業構造改革を推進する。また事業構造改革の一環として、2022年度末までに従業員数約1,300人を削減するとしている。
だからと言って、渋谷店まで閉店するという結論にはならない、とは思うのだが・・・
西武・そごうの親会社であるセブン&アイ・ホールディングスにとって、デパート業は本業ではない。あまたある子会社の中の一つでしかなく、グループ存続のためにドラスティックな判断をするのは、企業として当然のことである。
半世紀続いた渋谷戦争=東急vs西武だが、結局西武の退場による東急の不戦勝となるのだろうか。

デパート新聞編集長
連載 デパートのルネッサンスはどこにある?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月15 日号-第130回 池袋西武の初売りに行ってきた。脱デパートは非デパートなのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2026年01月01 日号-第129回 ジャパニーズホラー再考
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月15 日号-第128回 新宿伊勢丹に学ぶ
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年12月01 日号-第127回「モノ消費からコト消費」のその先は
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月15 日号-第126回 お化け屋敷はデパートの救世主なのか
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年11月01 日号-第125回 デパートを巡る様々なニュース 後追い記事の後を追う
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月15 日号-第124回 百貨店の閉店で街は寂れたのか?
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年10月01 日号-第123回 池袋西武の現在位置 ―代表と店長と―
- ヨドバシカメラの素質と資質
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年9月15 日号-第122 回 インバウンドバブルの終焉?