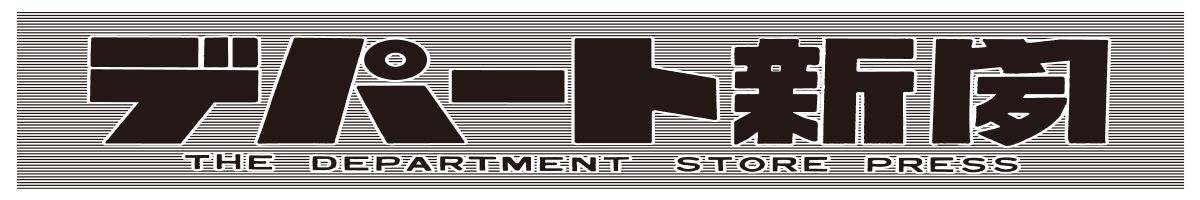デパート新聞 第2654号 – 令和2年12月15日

デパート新聞 第2654号 – 令和2年12月15日 1面 
デパート新聞 第2654号 – 令和2年12月15日 2面

デパート新聞 第2654号 – 令和2年12月15日 3面 
デパート新聞 第2654号 – 令和2年12月15日 4面
10月全国は1.7%減
日本百貨店協会は、令和2年10月の全国百貨店(調査対象73社、196店〈令和2年9月対比±0店〉)の売上高概況を発表した。売上高総額は3753億円余で、前年同月比マイナス1・7%(店舗数調整後/13か月連続マイナス)だった。
百貨店データ
- SC販売統計調査10月
- 都市規模別・地域別売上高伸長率
- 神奈川各店令和2年10月商品別売上高
- 2020年10月インバウンド売上、購買客数は9カ月連続のマイナス
地方百貨店の時代 その6
~ セール会場の在り方の歴史に学ぶ 貨幣価値の魔力(2) ~

デパート新聞社 社主
田中 潤
「商品に対して貨幣価値がすべてだと考えてはいけない」という思考は、いわゆるセールにおいて重要な示唆を与えている。正価品を売ることを基本としてきたデパートが正価品の値引きを始めた当初、定期的に行わ れた催しが大廉売であった。店内の様々な商品を催し物会場で一斉に値段を下げて販売するという企画であり、デパートの臨時的な収益源として大きな役割を担った。催事前のデパート内は、売り場からの商品の移動で大混乱を極めた。
デパートのオリジナル商品の値段が特定の時期だけ安くなるということは、他の商品との比較ではなく、その商品そのものの価値評価が行われていることに他ならずBtoC の関係は理想的であった。
また、日頃それぞれの売り場に陳列されていた見慣れた商品が一つの会場に一堂に並べられ、しかもすべてに赤札が付くというワクワク感は、消費者に非日常感を与えるには十分であった。プロパー(いつもの)売り場にはない喧騒感、その会場の中でのみ繰り返される店内放送は、いやがうえにも異様な購入意欲をかき立てていった。デパートのもつ特性を十分に活かして、商品そのものの価値を盛り上げていったのである。安売りは一つの大きな動機ではあるものの、必ずしも安いからそのモノを買うという単純な流れではなかったのである。
例えば、セール期間中に更にタイムサービスなどと称して、ある時間のみ商品を一定のステージに上げて紹介すれば、極端なことを言えば、それまで売り場に置いてあった時とほとんど同じ金額でも飛ぶように売れることも少なくなかった。
こうした現象が起った一つのポイントは、消化仕入を前提にしたセール用の商品数を抑えていたことだ。正価品とは異なり「本来この金額」という価格設定を意図的にした上でメーカーがどこかから特設会場に直接持ち込んだ商品には、消費者はオリジナリティーを感じない。付けてある価格だけが購入の判断基準となってしまうのである。
優れたバイヤーは、売り場の販売責任者と組んでいかに「正価品を値下げしました」という印象を顧客に与えるかに腐心した。その為には、セールをする数ヶ月前から場所を割いて、それらの商品を店頭に並べるなどの工夫がされた。
それに呼応して、ベテラン販売員は売り場で商品を吟味する顧客に「この商品は近くセールに出しますよ」という秘密情報を伝えるわけである。顧客を巻き込んで、ワクワクする買い物の演出を行っていた。
読者には、正価で売れるものをわざわざセールで購入させるのは、利益を減少させる行為ではないかと思われるかもしれない。しかし、オリジナル商品でも魅力が劣るものについては次の戦略を考えなければならない。つまり、その商品の販売予想を見極めて売れ残るリスクのある商品にはこうしたアプローチが行われたのであり、その手順は鍛えられた接客経験から導き出した販売員の決断を軸に行われたのである。裏を返せばプロパーで売切れる商品は絶対にセールには出さない、わけである。
さて、商品の価値にオリジナル性がなくなって久しい。もはやプロパー商品をどう売っていくかという戦略には、あまり意味がなくなってきている。しかし、地方百貨店においては、セール会場に限らず、売り場の中に遊びの場を作るということは決して出来ないことではない。いかに商品をさばくかだけを考えるのではなく、顧客が楽しめる催しを徹底的に取り入れていくことが肝要である。敢えて、顧客のために収益性のない企画を行うのである。それは販売員にとっては顧客と、いつもとは違う信頼関係を作るチャンスである。かつて、セール会場で行われたようなすべての価値観をしっかり見極め、コミュニケーションを最優先した場づくりを考えていくことが必要である。
朧

大学ラグビーの関東対抗戦は、明治が早稲田を振り切って優勝した。この2年間はこの対抗戦、全国大学選手権をこの2校が分け合ってきており、今年の全国大学選手権は、どちらが勝つか、或いは伏兵が現れるのか興味深い。大学ラグビーといえば、帝京の天下と思っていたが、いつのまにかいつもの顔ぶれが帰ってきていることをみても、時の移ろいの早さを感じさせられる。
ラグビーは、後ろにボールを渡しながら前へ進むところに最大の妙味がある。今年の日本は、新型コロナウイルスという予想外の事態で、今迄の発展志向から大きく舵を切り、定常型社会への第一歩を踏み出した。既に、数多くの価値観が変わってきている。ボールを後ろに廻す覚悟で、やがては前に進む国民力を作っていかなければならい。
連載:デパートのルネッサンはどこに有る? - 百貨店よ、どこへ行く
脱百貨店の表明〈髙島屋と大丸松坂屋〉
日経MJ11月2日号の「トップに聞く」は、髙島屋の村田社長へのインタビューを載せている。
タイトルは『百貨店はテナントの一つに』「東神開発がグループの軸」だ。
日経MJ11月25日の、今度は一面には『Jフロ ント「百貨店ごっこ」やめた』「自社売り場をテナントに」というタイトルが躍っている。「大丸心斎橋にパルコ開業」「若者呼ぶ強み|パルコの原点」と続き、J・フロントリテイリングの好本社長のインタビューが 掲載されている。聞き手はいずれも、日経MJの鈴木編集長だ。
本紙12月1日号の当欄にて、大手3大百貨店として、三越伊勢丹、髙島屋、大丸松坂屋(Jフロント)の現況を取り上げた。阪急阪神やそごう西武には申し訳ないが、売上規模とブランド力含め、我が国の3大百貨店 は名実ともに、上記3社であることに、疑いはない。
しかるにそのうちの2社は社長本人が、「百貨店を止める」「テナントの一つになる」と言っているのだ。名にし負わば、わがデパート新聞としては、見過ごせない記事だ。デパートのルネッサンスを探していたら、 いきなり「百貨店に未来はない」という話を聴かされたのだ。それも大手百貨店のトップ2人から。
さて、少し落ち着いて、このインタビューを読み進めたい。キーワードはやはり「テナント化」であり、髙島屋では東神開発、Jフロントではパルコが、グループの軸になるという。判で押した様に(この比喩がいつまで使えるかも気になるところだが)両社長とも、傘下の商業=不動産デベロッパーの名前を挙げた。まるで遺産相続人の指名のごとくだ。
百貨店のテナント化=ショッピングセンター化については、本紙でも何度か取り上げている。8月合併号では、百貨店の生き残り策の一例として、百貨店のSC化=テナント化を考察し、例として所沢と東戸塚の西武 S.C.を取り上げた。続いて9月1日号で、玉川髙島屋S・Cの約半世紀にわたる、百貨店と専門店(テナント)の複合業態の軌跡を取り上げている。
続きは デパートのルネッサンスはどこにある? 2020年12月15日号 を御覧ください。
無駄なこと part2 無駄と雑の違い

犬懸坂祇園
作詞、作曲などをしております
無駄と雑の定義
無駄なことと雑なことは似ているが、前者は「益のないこと」、後者は「粗くて念入りでないこと、丁寧でないさま」などと定義されている。無駄なこととは、一生懸命行ったのだが、結果として客観的には益がなかったことである。つまり、多くの場合、無駄なこととは丁寧に行われているのである。ここに、無駄と雑の決定的な違いがある。
一期一会
一期一会ということで、考えてみたい。この言葉は茶会の心得であり、生涯ただ一度まみえることを言い、だからこそその出会いに最大限集中すべきであるという教えである。一期一会は、まさに出会う当人同士が自らのすべてをかけて丁寧に相手と向き合うことであり、その多くは無駄なことなのかもしれない。しかし、その心はお互いを尊重しあうかけがえのないものなのである。一生懸命無駄なことをすればするだけ、相手に はそれが伝わり、こちらへの特別な意識が働く。こちらの思いやりが、伝わるのである。この時、「雑」には出る幕がない。むしろ、最も否定すべき概念といえよう。無駄とは、人とのコミュニケーションにおいて必須の心得なのである。デパートにおける接客の合理性が、どのくらい雑なことかと考えると…答は明白だろう。