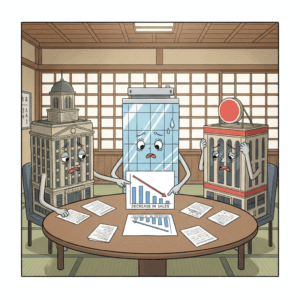デパートのルネッサンスはどこにある? 2025年9月15 日号-第122 回 インバウンドバブルの終焉?



訪日客が過去最高も都心4社は前年割れ
先ずは速報値から見ていこう。
インバウンド消費の大幅マイナスにより、大手百貨店の7月売上高は上位4社が前年を下回った。
訪日客が増加を続ける中、免税売上高は今年3月から5か月連続の減少となった。
詳細については、本紙9月1日号2面に掲載された「7月インバウンド売上高5か月連続減少」をご参照いただきたい。大手百貨店の7月売上高(既存店修正値)は、前年の免税売上の伸率が高かった反動から、大手4社ともに前年同月実績を下回った。
ラグジュアリーブランドなど高額品の不振が主な要因。尚、国内客の売上は前年を上回っており、都心百貨店でのインバウンド売上の減速が鮮明になった。
三越伊勢丹 ▲5・1%
2025年7月、伊勢丹新宿本店は7・3%減、三越銀座店は7・6%減だった。一方三越日本橋本店が1・1%増を確保した。
免税売上高は35・6%減で、前年売上が高水準だったことによる反動が大きかった。
国内客売上は3%と微増ながら、富裕層顧客を中心に秋物が動き始めた。
髙島屋 ▲3.8%
本年7月、玉川店は4・9%増だったものの、その他の大型店はすべて前年を下回った。京都店が9・1%減、新宿店が8・2%減、大阪店、横浜店が3・8%減となった。
本コラム8月1日号で言及した様に、二子玉川は「かろうじて」郊外店舗であり、前年のインバウンドの波が高くなかったためだと思われる。
全店の免税売上高は33%マイナスとなり、国内客は1・6%増だった。 焼け石に水、という表現を実感させられた。
大丸松坂屋 ▲0・4%
同7月の大丸梅田店は8・4%増、松坂屋名古屋店が改装効果により2・1%増となった。
梅田店はハイブランドからのスイッチが奏功し、アニメ、ゲーム等のキャラクターが好調で、新たなインバウンド需要を取り込んだ形だ。
渋谷パルコでのポケモン、任天堂といったゲーム関連での強みを、関西の旗艦店に移植する等、グループシナジーが寄与したと思われる。
それでも、免税売上高は30・1%減、国内客が3.3%増だった。
阪急阪神 ▲8・8%
7月は阪急うめだ本店が13・4%減で、免税売上高が40%マイナスだった事に加え、来春完成に向けた全館リニューアルによる改装工事の影響で苦戦した。
阪神梅田本店は7・5%増だった。改装効果により、ファッションとライフスタイルの商品カテゴリーは20%アップとなった。
大丸松坂屋の事情

各社の前年対比マイナスを比べると、単純に大丸松坂屋が比較的「軽微」な事が見て取れる。これは、前述した脱ラグジュアリー路線への転換以上に、元々のインバウンドシェアが高くなかったことが理由だ。山が高くなければ谷も深くはならない、ということだ。
大丸は、東京では新宿(伊勢丹、髙島屋)、銀座(三越、松屋)、ではなく東京駅に。名古屋は駅直結(髙島屋)ではなく栄(松坂屋)に位置している。
そして大阪では大丸心斎橋店も梅田店も、うめだ阪急や大阪髙島屋(難波)の後塵を拝している。実際に2024年度の百貨店売上ランキングでも、J.フロントリテイリングでベスト10にランクインしたのは、8位の名古屋松坂屋だけだ。
因みに大丸の売上高NO.1の心斎橋店は12位だ。ラグジュアリーブランドを求めるインバウンド客は、交通の要衝に位置し、多くのブランドを集積する「強い街の強い店」に集中する。
訪日客は増加も百貨店はマイナス
日本を訪れる外国人観光客は、今年1月から5月にかけて1814万人(前年同期比23・9%増)と、過去最高を記録した昨年の同じ期間よりさらに349万人増えた。滞在中の買物に使う支出額も増加傾向にある。訪日客は今も増加し続けているのだ。
但し、例えば髙島屋は国内で営業する百貨店12店舗のうち、日本橋と柏を除く10店舗で、今年3月から5月までの総額売上高が前年割れとなった。
この半年で、インバウンド消費の「百貨店離れ」は静かに進行している。日本百貨店協会の調査によると、2025年5月の百貨店免税品総売上高は425億円で、前年同月比40.8%の大幅減となった。
前述したが、免税品の売上は3月以降、一度も前年をクリア出来ず、3月は10.77%減、4月は26.7%減と、減少幅は月を追うごとに拡大、インバウンド消費の減速に歯止めがかからない状況だ。
なぜ百貨店はインバウンド不振に陥ってしまったのか。昨年を振り返ってみよう。
爆買い呼んだ円安
百貨店業界では新型コロナウイルスの水際対策が緩和されてから、免税品の売上は急回復した。昨年の百貨店全体の年間売上高が6487億円(前年比31.1%増)。
コロナ禍前(2019年)の3461億円を大幅に上回り、2年連続で過去最高を更新している。
その好調を支えた大きな要因が円安だ。
2023年12月に1ドル140円台で推移していた為替相場は、2024 年6月ごろまでに160円台近くまで進んだ。これに比例して、月ごとの免税品の売上高も増加した。
その後、円安基調は一時落ち着いたものの、昨年12月から翌1月ごろにかけて再び160円台に近づくと、免税品の売上高も再び増加に転じた。円安になれば、訪日客は日本を訪れて「円」で購入する方が割安な状況となり、結果として、百貨店では特に高級ブランドや宝飾などの高額品が、飛ぶように売れた。
2024年上期には、ブランド品の値上げ前の駆け込み需要も加わり、2024年5月の1カ月間には718億円の免税品売上高を記録。
前の年の同じ月と比べて約2.3倍の増加となるなど、異常な盛り上がりとなった。
業績見通しを下方修正
さて、今年に戻って話を続けよう。
日本最大の売上高を誇る伊勢丹新宿店でも、インバウンド消費が減速し、2025年4~6月までの総額売上高(速報値)は前年同期比で5.5%減少となった。
状況が一変したのは2025年2月ごろからだ。為替が円高基調に転じると、日本円で高額品を購入する際の割安感が薄れた。
ハイブランドの値上げ前の駆け込み購入の反動もあり、免税品の売上は徐々に減少し始めた。
前述した様に、訪日客消費の減速は、すでに大手百貨店の業績に大きく影響している。
高島屋は6月末、2026年2月期の第1四半期決算発表に合わせて、通期業績予想を下方修正した。
修正後の会社計画は、売上高にあたる営業収益が4930億円(前期比1.1%減)、営業利益が500億円(同13%減)。減収、営業減益となれば、新型コロナウイルスの感染が拡大した2021年2月期以来、実に5年ぶりとなる。
特殊な事例
筆者は、デパート業界を巡るアフターコロナの2020~2025年のこうした動きを、ちょっと特殊な事例だと考えている。
今回のインバウンドバブル、と呼ばれる百貨店への恩恵は長く続く、という前提でいること自体、かつて高度経済成長と呼ばれた時代と同様なのだと思っている。
ちょっと前まで、日本は「失われた30年」と言われていた。
※今もそうかもしれないが。
バブル崩壊、9・11、リーマンショック、東日本大震災、そしてコロナ禍を経て、自然災害やそれを上回る「人的」災害により、日本経済の長期停滞、そして低迷を表す言葉だ。
これに対して2023年、2024年は、「2019年度を上回る」から「過去最高益を更新」という、インバウンド景気による都心大手百貨店の躍進を伝える惹じ ゃっく句 がメディアを賑わせた。
30年以上「鳴かず飛ばず」だった百貨店が、外国人観光客の爆買い(この言葉もなるべく使いたくないが)により、売上が飛躍的に伸び、高収益を達成したことは事実だし、それを喜び、称賛することにやぶさかではない。
が、それもトランプ関税や円高のせいで「短い春」で終わってしまった、と扱うメディアも増えて来た。
インバウンド偏重の危機
本紙本コラムでは「耳タコ」級に言っているが、インバウンドバブルは、そもそも一部都心の大手百貨店だけに恩恵のあったフロックであり、存亡の危機にさらされている地方百貨店にとっては最初から「無かった」のだ。もちろん商売だから、買ってくれる人がいれば、仕入れるし、売りまくりたいのは当然だが、デパート業界全体が再び盛り上がっていた訳ではない。
インバウンドが、閉店の瀬戸際にいる地方百貨店を少しでも「延命」した訳ではないのだ。
本コラムで松屋銀座100周年取材した際も、(本紙5月15日号2~3面に掲載)松屋の古屋社長の提唱する「インバウンド一本足打法」の危うさを説いた。
※以下再掲載
筆者の担当する4面コラム「デパートのルネッサンスはどこにある?」の5月1日号でも言及しているが、昨年2024年は確かにインバウンド景気の高まりにより、都心の大手百貨店は軒並み「過去最高益」を更新し続けた。
但し前述した世界情勢の変化により、直近2か月のインバウンド売上には早くも「翳り」が見え始めている。パンデミックからの捲土重来を果たした都心デパートにも、トランプショックの影響は出始めているのだ。
「プレミアムリテーラー」や「グローバルデスティネーション」は松屋銀座「だからこそ」の価値である。
地震も戦争も不景気もパンデミックも乗り越えた、と胸を張るのは結構だが、インバウンドの一本足打法は「危ういのでは?」と危惧している。お祝いに水を差す様で申し訳ないが。
筆者はインバウンド復活に縁がなく、忘れられたまま、次々と閉店していく地方の中規模百貨店をいくつも見て来ているからだ。以上5/15号再掲載
多くの富裕層を抱える日本一の「都心」に位置する松屋銀座だからこそ、インバウンドの翳りは多大なマイナス影響につながる。
トランプショックに限らないが、42000円台を付けた日経平均株価がいつまた3万円台に逆戻りするやもしれない。
物価高の現在、株価が下がると、即購買力は落ちる。それは給料が上がらない中間層だけでなく、都心デパートが頼る富裕層でさえも例外ではない。やっと戻って来た中国人観光客も、140円台を推移する円高基調や中国経済の減速を背景に、「爆買い」は過去の現象になった、という観測も増えている。
インバウンドの限界
長々と説明してきたが、筆者はいったい何が言いたいのかと言うと、景気の良い時だけを基準にして、商売をしていると危ういですよ、という事なのだ。
日本におけるバブル経済は、土地バブル、ITバブルもインバウンドバブルも含めて「未来永劫続くモノ」という幻想は、持たない方が良いですよ、という至極真っ当な結論だ。
外国人観光客が、円安を背景に、ハイブランドを買いまくるのであれば、都心デパートは売りまくれば良いし、顧客化した富裕層を優遇しCRM政策を強化するのも間違っていない。
用語解説: CRM(Customer RelationshipManagement /顧客関係管理)は、企業が顧客との関係を構築・維持・強化するための戦略やシステムのこと。ざっくり言えば「顧客とのつながりを深めて、ビジネスを成長させるための仕組み」。
※パソコンのAIが答えてくれたまま書いたのだが、彼は(彼女なのか?)「ざっくり言えば」と宣のたまう。勝手に「ざっくり」してくれたのだ。いや、親切心からなのか。詳細に知りたい場合は「詳細に」とAIへの質問時に書くべきらしい。
失礼、脱線した。この辺のAIを巡る議論はまた別の機会に。
要するに、商売(事業)は「今が良ければ良い」だけでは危険ではないか、という事なのだ。これは、百貨店に限らず、どんなビジネスでもそうであろう。只(あくまで私見だが)デパートに従事する人びとは、概して「変化を嫌う」傾向が強いのではないかと思っている。
前年比の呪縛
デパートパーソンの現場は常に、日々の売上、週毎のシフト、月々の催事企画、シーズン毎のファッションテーマ、半期ごとの処分セール、年度決算、そして何より「前年対比」という亡霊におびえながら過ごしているからではないかと思う。
※この「亡霊」という表現は、現場で販売や企画をした人間には決して大げさではなく、実感として感じるモノだと思う。
前年比という亡霊は、デパート人に付きまとい「去年は、こうだったのに」という幻影を見せつけてくるからだ。この呪縛から逃れるのは「前年達成」という護符だけなのだ。
だから、と続けるのも変なのだが、経営トップが、しっかりと「5年10年後の我がデパートのあるべき姿」ビジョンともいうべきモノを掲げていないと、すぐに本紙の様な外野から「目先しか見ていない」と非難されてしまうのだ。
地方の逆襲
それでも、人口減少で客が減る地方と、一極集中で客数を維持し、更にインバウンドで客が(例え一時的でも)増えた都心のデパートでは、状況は天と地ほど異なる。弊社(デパート新聞社)が「地方デパートの逆襲(カウンターアタック、CA)プロジェクト」を推進しているのも、そうした瀕死に近い状況の地方百貨店の手助けをしたいからだ。
本紙は、地方デパートがなくなる、ということは、そのエリアに住む人びとにとっては「文化のランドマーク」の消失につながると考えるからだ。
大変失礼ながら、ヨーカ堂やイオンが、出店したり撤退したりするのと、百貨店の閉店はいささか地元の反応が異なる。
これを「文化拠点の喪失」と呼ぶのがおこがましいのであれば、単なるノスタルジーでも良い。デパートの消失は地元住民に「不便になって嫌だな」以外の情緒を呼び起こすのだ。
口幅ったいが、業界新聞である本紙は、地方デパートに企画協力することで、その地方で生活する住民をサポートしたいと考えたのが「地方デパートCAプロジェクト」であり、それを一歩進めた、というか、もう一歩生活者に寄り添ったのが「暮らしのカウンターアタック(CA)プロジェクト」だ。
CAの拡大
これは、三重県津市の松菱百貨店で培ったCAプロジェクトの成功事例を、全国の地方デパートでも展開して行こうという目論見だ。
この夏、鳥取県のJU米子髙島屋や兵庫県姫路市の山陽百貨店で「選べるガチャガチャランド」の展開(短期催事)を実施した。
地方デパートを再生したい、という思いは、地方(住民も含めた)そのものを生き残らせたいという思いでもあるが、それは生半可に達成可能な命題、使命でない事は、わかっている。
業界新聞一紙が単独で達成出来る目標ではない。只、そうした有志が結集すれば、地方デパートを少なくとも「しばらく継続」出来る可能性は高まるのではないだろうか。
もちろん単なる「延命」では意味がないことも、承知しているつもりだ。地方都市における商業の疲弊は、文化の衰退につながる。それが今、日本全国の「地方」で起こっている事だ。
筆者は、一極集中が「悪」で地方再生が「善」だと言う様な、単純な二元論で話しているのではない。
地方の住民は、自分たちの住んでいる地域をどうしたいのか、という問題だ。先ずはそこを各々が考え、議論しなければならないのだ。
そして、地方百貨店は、自らが「地方の一員であるという自覚」が必要だ。それは覚悟と言い直しても良い。
筆者の私見だが、百貨店の覚悟は、ちょっとだけ心許ない。皆が皆そうではないとは思うが。

デパート新聞編集長