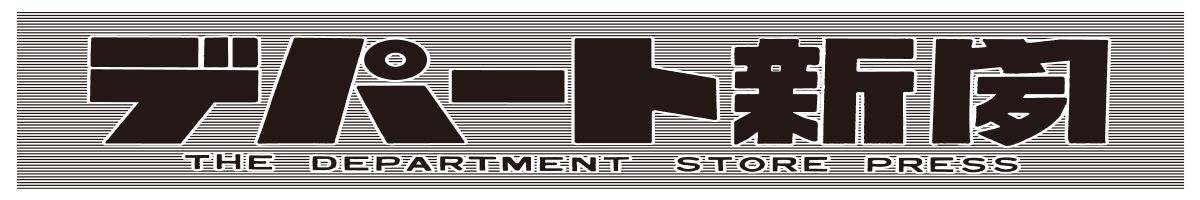特集「大沼」 - 2020年4月15日号

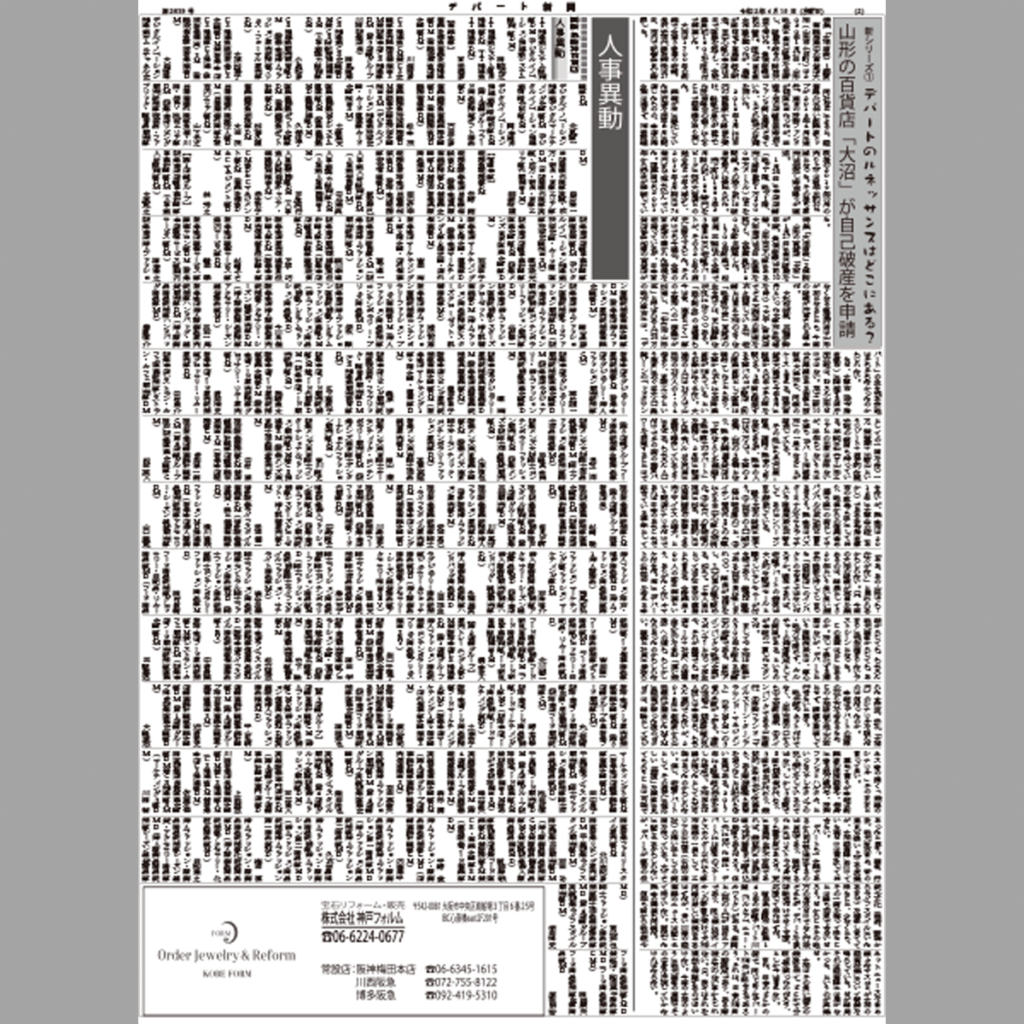
特集「大沼破綻」1概要
営業再建中の百貨店大沼(山形市七日町)は2020年1月27日、山形地裁に自己破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けた。負債総額は約30億円。同社は当初自主再建を図ったが、集客が回復せず事業継続を断念。市中心部の本店は26日で営業を終了し、全従業員約190人を同日付で解雇した。
大沼は1700年の創業で全国3番目の老舗。長沢光洋代表取締役は27日、市内で記者会見し謝罪した。
同社などによると、経営悪化に伴い創業家トップが2018年4月に退任。東京の投資ファンドが経営に当たったが、出資予定の店舗改装資金をファンド側に還流させていた、とされ地元の反発を招いた。
2019年3月には市内の実業家から融資を受け、幹部社員らが設立した投資組合の傘下に入ることで経営権を取り戻した。
業績が特に悪化していた米沢店を同年8月に閉店したものの、本店の再生策は進まず、消費税増税後の2020年10月の売り上げは前年比約30%減となった。その後も販売は低迷し資金繰りが逼迫。
1月26日に本店店舗(地上7階、地下1階、売り場面積約12000平方メートル)などを閉鎖。その取り扱いは破産管財人に委ねられた。
売上高は1993年2月期の約196億円をピークに郊外大型店との競合などで年々減少し、2019年2月期には74億円まで落ち込んでいた。採算面でも2001年から赤字が継続していた。
特集「大沼破綻」2解説
山形の百貨店「大沼」が1月27日に自己破産を申請。負債総額は約30億。山形市中心部にある大沼本店は26日に営業を終了し、全従業員約190人を即日解雇した。
1700年創業で、松坂屋、三越に次ぐ全国で3番目に古い老舗デパートが、その320年の歴史に幕を下ろした。それだけでも今現在、全国の百貨店の置かれた苦境を物語っているが、日本百貨店協会加盟の百貨店がなくなる都道府県は山形が初となることも、今回の破綻が注目される理由だ。
大丸松坂屋、三越伊勢丹といった大都市に地場を持つ「大手」百貨店でさえ不振店の撤退を次々発表している中、老舗とは言え大沼のような「地場独立系」百貨店の生き残りは、更に困難な状況になりつつある。「地方創生」のお題目も今は昔、東京とごく一部の大都市への一極集中が加速し、「仙台市山形区」と呼ばれる人口25万の地方都市には、「デパート」の生き残る余地はそもそもなかったのかもしれない。
ただ、大都市(政令指定都市)に隣接する県庁所在地は、むろん山形だけではない。JRで二駅10分の距離にある京都と滋賀県大津市も、同様のケースと言える。西武百貨店大津店も今年8月に開業から43年でその幕を閉じる。3年前に隣接する大津パルコが閉店(別の商業施設として営業は継続)したこともあり、大津から次々に大手商業施設が消えている、という印象はぬぐえない。大津市の人口は34万人で山形市の25万人の1.34倍あり、京阪エリアという東京に次ぐ巨大人口集積ゾーンのベッドタウンとしての一面を持つ一方、琵琶湖+比叡山というリゾート+歴史的な観光地の側面も持っている。単純に仙台=山形エリアとの比較は出来ないが、半年もしないうちに大津も「デパート消滅都市」の一員となることが確定している。
その他にも名古屋=岐阜、福岡=熊本のような例もあるが、熊本の人口は74万人で、大津の2倍強、山形の3倍弱となり、熊本の鶴屋百貨店は「上質なくらしを提案する熊本郷土のデパート」を標榜し、2月末に閉店した熊本パルコを尻目に堅調を維持しているように見える。もちろん人口だけでその街の購買パワーを評価することはできないが、熊本市は2012年に大都会の証(あかし)である政令指定都市の称号も手にしており、地震からの復興含め「勝ち組」の街としてサバイバルの成功例と言えるだろう。熊本市はバスターミナルをサクラマチという商業施設に衣替えして、あのロンハーマンまで誘致している。
話を大沼の破綻に戻そう。①山形市の人口減少(特に若年層の)と、②イオン等郊外SCの台頭による市中心部の空洞化。③仙台への買物客の流出に加え、短期的には④消費増税の影響による売上マイナスの増大、という閉店シナリオだけであれば日本のあちこちで起きている事象として「ああ、あの山形でも・・仕方がない」と思われるかもしれない。只、今回の大沼の破綻が耳目を集めるのは、結果として320年という長い長い歴史の晩節を汚してしまった「突然閉店」のインパクトの大きさではないだろうか。通常であれば、老舗デパートの最後は大々的な閉店セールと賑々しいセレモニーが付き物であり、最後は顧客である山形市民に惜しまれつつ、館長が挨拶をし、入口の扉の鍵を閉める。加えて、ご本人達にとっては正に青天の霹靂とも言える、全従業員190人の即日解雇という、ありがたくないオマケ付きだ。常に「デパートの公益性」を考える本紙からしても、もちろん地元顧客からしても、あまりに残念極まりないラストシーンとなった。
この原因はどこにあるのか。決して美化する意図はないが、デパートという商業施設には、都心・地方を問わず、カルチャーの発信拠点としての側面がある、というのが本紙の一貫したスタンスだ。
ましてや大沼は創業から300年を超える老舗中の老舗である。当然メインバンクや地元企業がスポンサーとなって再生や、それが無理でも、閉店セール+社員への退職金支払いを含む「潔い最後」への道も、もしかしたらあったのかもしれない。顧客と社員に看取られた大往生、失礼「大団円」のシナリオを阻んだのは何だったのか。
本紙はデパートの将来の在り方を考えるため、この大沼破綻を他山の石とせず、課題を整理して行きたいと思う。
地元紙やネットだけでなく、山形市民の口からも①大沼創業家、②メインバンクである山形銀行、③投資ファンド「マイルストーン・ターンアラウンド・マネジメント」(以下MTM)の3者の名前が上がる。本紙の性格上、経営破綻の犯人捜しは本意でも、もちろん目的でもないが、2018年に創業家から山形銀行が選定したMTMに経営が移った後のゴタゴタは、結論としてビジネス書の描く「最悪のシナリオ」そのままと言って良い。
重ねて言うが本紙は創業家の同族経営や、保身に走る地方銀行や、投資ファンド=ハゲタカ、といったステレオタイプの犯人探しをしているのではない。しかし3年間で5回も経営者が代わり、3回も株主が代わり、最終的に取引先も従業員も、ある意味顧客も損害を被ったことは紛れもない事実である。2017年に4期連続の赤字を出した時点で、大沼再生は誰が担ったとしても不可能であったのかもしれない。但し、老舗デパートとして、その歴史に相応しい「最後」を顧客に見てもらうことは可能であったと思う。顧客、行政、地元有志含め、皆の意見を吸い上げる度量が、大沼経営陣に欠けていた事だけは言及しておきたい。
デパートも一企業であるから利益を追求するのは当然であり、継続するためにはリストラや身売りも選択肢であろう。更に事業再生が不可能であれば、最終的には私的整理や法的整理まで踏み込む局面もあるだろう。但し先に述べた様に、デパートには通常のステークスホルダー以外にも都市商業の一員として、エリアの公益性(公共の福祉)の担い手としての側面を持っている。大げさに聞こえるかもしれないが、デパートが都市の伝統や文化(美術、芸能からライフスタイルにいたるまで)を継承し育てて来たこと、少なくとも、その一翼を担って来たことは誰も否定できないだろう。だからこそその地方の有志だけでなく行政さえもが、デパートを損得勘定だけでなく支援、応援して来たはずだ。
岩手県盛岡市に創業140年の老舗デパート川徳(パルクアベニュー・カワトク)がある。盛岡と山形の人口がほぼニアであり、同じ様に郊外イオンの影響を受けて大沼同様の厳しい環境にあるはずだが、幸い川徳の経営難のニュースは聞こえて来ていない。前述した熊本の鶴屋も同様だ。
何年も前から地元紙やネットニュースを含め様々なマスコミが大沼の経営状態について警鐘を鳴らしていた。だが結局それは経営陣には届かなかった、というのが実態だ。
大沼はその長い歴史の最後に来て、どこかで分岐点を誤ったのだろう、としか今は言えない。
また、日本のどこかの街で、同じようなデパート消失が起きるであろう。それは、日本の消費の転換点であり、ある意味仕方のない事かもしれない。只、我々はそれを漫然と傍観するのではいけない。今回の大沼のように地元顧客の目線でその中身を注視していかなければならない。