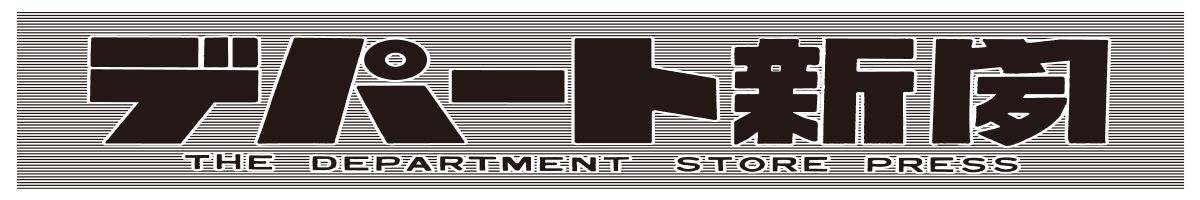デパートのルネッサンスはどこにある? 2020年08月01日号-7
コロナ禍で生き残りを模索するデパート
コロナ第2波襲来?
緊急事態宣言の全面解除から、ほぼ2ヶ月が経ったが、ここのところ連日「全国的な感染者数の記録更新」が続いている。まぎれもなく、コロナウィルス感染の第2波である、と断じる学者もいる。
特に首都東京では7月23日の新規感染者が300人を超えた。もはやアベノマスクの配布以上の愚策として、評判の悪い「Go Toキャンペーン」からも東京は除外された。
こうした状況となっても、安倍首相はじめ政府は、新たな対策もせず、発信すらしようとしない。菅官房長官にいたっては「東京問題」という、ある意味秀逸なネーミングで、本来は、国家の危機的な大問題を、東京に押し付け矮小化してみせただけだ。もちろん、言い逃れだけして、一切責任を取らない、というのは現政権の得意技なので、今さら驚くには当たらないが。
「経済」という歯車を回しながら、同時に感染防止をする事は「アクセルとブレーキを同時に踏む」と揶揄されているが、ハンドルを握っているのが現政権であるなら、後部座席にいる国民は、どうやって「自衛」をすれば良いのだろう。個々の国民の感染やひいては貧困化まで、自己責任、とでも言うのだろうか。
コロナが分けた明暗
前号で、宣言解除により再開した百貨店の状況を、地域ごとに、また業種や店舗ロケーションにより、売上の格差は非常に大きい、と伝えた。
食料品(デパ地下)の様に、コロナ影響をほぼ受けなかった業種もあれば、化粧品の様に、百貨店ならではの対面接客が出来ず、従来の販売手法の見直しを迫られた業種もある。
一方、デパート内で、比較的人気が高かったレストラン街については、感染による重症化リスクを懸念した、高齢者層の減少により、路面店同様、中々顧客が戻って来ない。
もう一つ、不要不急の代名詞である百貨店の中で、主力の衣料品も不振を極めている。ファッションにはシーズン毎にトレンドがあり、春物を買い逃した顧客が、6~7月になって夏物と一緒に春物を購入する理由はないからだ。必要なモノは、近所のユニクロやGU、しまむらで既に「間に合わせて」いるのだ。
では、小売が総崩れかと言うと、さにあらず、郊外のGMSやアウトレットモールは堅調だ。郊外モールは他人とのディスタンスを比較的とりやすい。それを利点として捉えるファミリー客が、いち早く回帰した。
コロナ前には、さほどストレスとは感じなかった混雑や行列が、今は「悪」となった。コロナ中に、近所のスーパーでの買物にさえ、ストレスを感じていた客は、百貨店の立地や接客、品揃えよりも、郊外モールの「解放感」を選んだのだ。
衰退のカウントダウン
百貨店の衰退と危機については、コロナの前から取り沙汰されていた。
繰り返しになるが、山形の老舗デパート大沼は、本年1月に創業320年の歴史に幕を降ろした。同月に天満屋広島アルパーク店、3月には新潟三越、ほの国百貨店(愛知)が閉店。以上がコロナ前。
この後も、8月には高島屋港南台店(横浜市)、西武岡﨑店(愛知)、西武大津店(滋賀)、そごう西神店(兵庫)、そごう徳島店が閉店する。これで徳島も山形に続き、デパート消滅県に名を連ねることとなった。また、来年2月に、そごう川口店(埼玉)、三越恵比寿店、同年9月には松坂屋豊田店(愛知)も閉店を発表している。
特に地方都市での百貨店運営の困難さは、コロナ禍により、更に強まり、その衰退のスピードは更に速まったと言って良いだろう。
百貨店のテナント化
本紙は「デパート業界新聞」として、公益事業としてのデパート運営の支援を標榜している。従ってニュースとして、百貨店の閉店を伝えるだけでなく、逆に「どうすれば百貨店は生き残ることができるのか」を考えて行きたい。
百貨店の「生き残り策」の一例として標題の「テナント化」を考える。ショッピングセンター化とも呼ばれるが、実態としては従来百貨店自身が自主編集していた売り場に代わり、その区画にテナントを誘致し、ショップの運営を任せることだ。
今までも、ブランドショップや飲食店、食品総菜店など、この方式を併用していたが、近年テナントシェアは増大の一途を辿っている。都心一等地の有名百貨店でさえ、ロフト、ユニクロ、無印良品、ニトリ等のメガストアを誘致する例が増えている。
デパート側は大型の集客核が増え、周辺商品の需要喚起に繋がる上に、大幅な人件費削減の達成が可能である。顧客側も生活必需品が、交通至便な駅前で手に入るのだから、運営側、消費者側ともにWIN-WINな結果と言える。
6月上旬にリニューアルが完成した西武東戸塚S.C.はテナント化した百貨店の典型例だろう。これは前年11月に一足先にリニューアルを終えた西武所沢S.C.に次ぐ西武・そごうのショッピングセンター型百貨店の2号店だ。所沢店のリニューアルオープンの様子は、テレビ東京の番組「ワールドビジネスサテライト」で取り上げられた。テレビ画面に映し出されたキャプションは「苦境の郊外型百貨店!ハイブリッド型が切り札に?」だった。
所沢西武S.C.の目玉は大型家電量販店である「ビックカメラ」に丸々ワンフロアを与えた事だろう。これには伏線として、所沢イオンの閉店によるヤマダ電機の撤退があり、結果として、駅前の大型家電の空白を埋めるベストタイミングとなった。その他に、かつては同じ西武セゾングループであったロフト、無印良品をはじめ、GU、ユザワヤ、ABCマート含め120店舗を導入した。これでB1Fの食品から2,3Fのレディスファッションゾーンを除き、館全体の75%をテナントに譲り、定借化した。
パルコ化ルミネ化?
「本業である」百貨店の自主編成売り場を、1/4に縮小した西武S.C.は、今やセブン&アイホールディングス傘下である。彼らにとっては「生き残り戦略」としてのテナント化に、何ら違和感がないのかもしれない。但し、例えテレビ局が「ハイブリッド型百貨店」と、もてはやしても、筆者の目には「もはやデパートとは呼べないのではないか」という思いが強い。
生き残りをかける「サバイバル」には、何が何でも、「なりふり構わず」という強い意志が必要なことは、認めざるを得ない。只、そもそも「なりふりをを構う」文化を育てて来たのが、日本のデパートの歴史ではなかったのか。いいがかりに聞こえたら申し訳ないが、顧客とともに、地域のために、そのエリアの文化を担う役割が、公器としてのデパートには、必要ではなかったのか、と思う。
今回西武が導入したテナントは、いずれも生活密着MDであり、デパートのもつ「ハレ=非日常」のエッセンスが、25%では少なすぎるのでは、と感じてしまう。
デパートは、只生き残れば良い、のではなく、生き残る価値があるのか、が今、問われている。
他社が既に実施している手法を、「なぞる」ことが、百貨店を支持している、顧客の信頼に応えることになるのか、今一度考えて欲しい。
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2024年02月15日号-86
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2024年02月01日号-85
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2024年01月15日号-84
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2024年01月01日号-83
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2023年12月15日号-82
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2023年12月01日号-81
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2023年11月15日号-80
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2023年11月01日号-79
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2023年10月15日号-78
- デパートのルネッサンスはどこにある? 2023年10月01日号-77